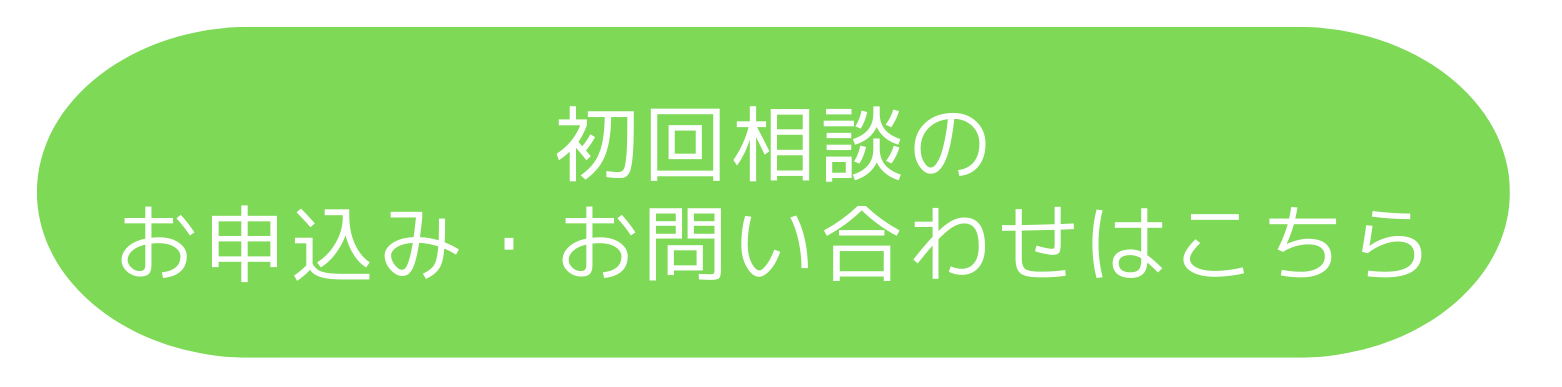2025年7月最新!【会社設立の費用】「誰に?」「いつ?」「いくら払うの?」税理士が「円単位まで」解説!
「会社設立の費用はいくらかかるのか」でお悩みではありませんか?
はじめての会社設立で、必要な費用がどれくらいなのか気になりますよね。
先に結論から言ってしまうと、株式会社の場合、
- 自分で全部やる場合:27万7,370円
- 司法書士さんに依頼する場合:28万2,370円
となります(実際にかかった費用)。
多くの起業家が「安く設立したい」と考えて失敗するケースがあります。
例えば、知人から休眠会社を譲り受けて設立費用を抑えようとしたものの、隠れた債務や未処理の業務があり、後から余計なお金がかかってしまうこともあります。

この記事では、会社設立に必要な費用を「誰に」「いくら」「いつ」支払うのか、1円単位で詳しく解説します。
登録免許税や定款認証料などの法定費用から、実印作成費、税理士や行政書士などの専門家への報酬まで、すべての内訳を明確にお伝えします。
株式会社と合同会社、それぞれの形態による違いや特徴、メリット・デメリット、必要な資料や手続きも徹底的にチェックしましょう。
また社会保険や納税の義務、代表社員や出資者の役割、許認可などの申請が必要なビジネスの注意点まで網羅しておきましょう。
さらに、補助金や助成金などの制度を活用して設立費用を半額に抑える方法や、オフィスや店舗の選択、ソフト導入、実績づくりなど、規模や業界ごとに異なる準備についても説明しています。
会社設立後の維持費用や、家を事務所として用いる場合の注意点なども解説します。

どの段階で行政書士や税理士に依頼すべきか、そのタイミングや理由、枚数の多い書類の効率的な準備方法、開業届との違いなど、会社設立に役立つ情報をさまざま用意しました。
会社を取り巻くルールである会社法の基本から、給与システムの選び方、可能性を広げるための選択肢まで、すべてを解説します。
ここで、念のため会社設立手続きの流れについても復習しておきましょう。会社設立手続きの流れについて動画でも解説しています。
※会社設立費用の詳細についてすぐに知りたい場合は、この動画は飛ばしてもらって大丈夫です。
会社設立・経営については、知らないと損することがとても多いのです。
間違った情報に流されてお金を失う経営者を一人でも助けたい!という強い想いでこの記事を書いています。
会社設立で
・合法的に節税する方法
・売り上げが増えなくても手取りのお金を増やす方法
・役員報酬の決め方
などを
で配信中です。
この記事は次のような人に読まれています。
- これから事業を始めるために会社を設立したい。
- すでに個人事業主として事業を行っていたけど、税金の支払いが大変になる前に「法人(会社)」として事業を行うこと(法人成り(ほうじんなり))を検討している。
- 友人から休眠会社を買い取って、会社の設立費用を浮かせようと思っているが問題がないか知りたい。
このようなお悩みをお持ちの方向けに、
会社を設立するには
- 誰に?
- いつ?
- いくら払うのか?
について解説していきます。
誰に?
会社を設立するにあたってサポートしてくれたり、会社を設立するために国が決めた税金のようなものがあったり・・・
いつ?
会社を作る何か月も前だったり、会社設立した後でよかったり・・・
いくら払うのか?
「ざっくりいくらぐらいか」また「円単位まで具体的に」説明しています。
なぜ私がこの説明をするのか?
それは、会社設立だけでなく、経営はすべて「投資」から始まるから。投資金額がいくらであるかを知っておくことは経営を始めるにあたって、とても重要になります。
そして、「過剰に初期投資を減らそうとすることが間違っているのでは?」ということに気付いていただきたいからです。
ちなみに、起業しても残念ながら稼げない人の共通点がひとつあります。それは、
・稼げないこと
・繰り返し行動しないこと
なのに
スキルの習得にお金と時間をかけてしまう
こと。
もっと言うと、体力や気力を分散させてしまうことなんです。
つまり、会社設立について詳しくなるよりも、本業に集中して!!と言いたい。

だから、この記事を読んでさらっと会社設立しちゃってくださいね。
会社設立に詳しくなっても、あなたが稼ぐことにはつながらないので・・・
さて、会社設立費用は、
①あなたが誰にも頼らず自分で会社設立手続きをした場合
②専門家に依頼した場合
で費用が違うという事実はご存知でしょうか?
株式会社を設立する場合と合同会社を設立する場合についても会社設立費用の金額は違ってきます。
※設立する会社の種類によって、会社設立費用は異なります。
(ネタバレしますが…自分で手続きをしても、実はあまり安くはなりません!)
この記事ではこれから会社を設立するあなたが「計画的にお金の準備をするために」会社設立にかかる費用を解説していきます。
ちなみに、会社設立については動画でも解説しています。
・法人成りのタイミング
・合同会社で法人成りするの注意点
・法人成りの手続きで節税できる8項目
など
これから会社を設立するか検討中のあなたが手ガネ(手元に残るお金)を増やす方法について徹底的に動画で語っています。
設立にかかるお金について、「誰に」「いくら」「いつ」払うのかをすべてまとめてみたので一緒に見ていきましょう。
ややこしいことは抜きにして、直接教えてほしい!という場合は、こちらのお問い合わせフォームから質問をしてください。
会社を設立する費用・・・ズバリいくら?
純粋に会社を作るための費用・・・25万円~30万円(株式会社の場合)
※経営を始めるための初期費用(イニシャルコスト)とは分けて考えます。
会社設立の「費用」というと、一般的にはこの2つを指しますが、この記事で「会社という『箱』を作るための費用」に限定して解説していきますね。
会社設立費用の内容を詳しく見ていくと…
- 資本金(しほんきん)
- 税金(ぜいきん)
- 移動代(主に交通費)
の3つに分けられます。
※資本金は、費用ではありませんが、「ひとまず準備しておく必要があるお金」「財布から(いったん)出るお金」という意味で分類しています。
会社設立に必要な費用は結局いくら・・・?

自分でやってもプロに頼んでも、28万円ぐらいはかかる、ということになります。
会社設立前後に、だいたいこれぐらいの支払いがあると考えておいてください。
ただ、司法書士さんに依頼した場合には、自分でやる手間が省けるので、トータルで考えると司法書士に依頼した方が得、と考えることができます。
※しかも、司法書士さんが各種支払いを代行してくれて、あなたはお金の払いを遅くすることができる場合があるので、少しでも資金繰りが楽になります。
※会社設立後に融資を受ける場合には次の記事を参考にしてください。
会社設立費用の前提「設立手続き」を知る
「会社設立」は、ざっくり言うと次の手続きを行います。
- 印鑑を作る
- 定款(会社の社内ルール)を作成し、認証(認定のようなもの)を受ける
- 資本金を振り込む
- 法務局に書類を提出する
少し細かく説明すると・・・
- 印鑑を作る:会社名を決定して、印鑑を発注
- 定款を作成する:会社の基本事項(※1)を決定し、定款を作成(※2)
その後、
- 【公証役場にて】 定款の認証を受ける(「設立登記申請書」も作成)
- 【銀行にて】 個人の口座に資本金を振込(振込後、通帳をコピー)
- 【法務局にて】 設立日に法務局へ。登記完了後、1週間ほどして謄本と印鑑証明書をもらう(※3)
設立手続きはこのような流れになります。
※1 事業目的、本店所在地、資本金、発起人(出資者)、役員構成など
※2 出資者(普通は社長になる人のことです)の「個人の」印鑑証明書を最低2通、取得しておく必要があります。
※3 謄本と印鑑証明書をもらったあと、普通は法人の銀行口座を開設します。税務署や年金事務所の手続きも忘れずに。
以上が、会社を設立するための手続きです。
では、このうちお金がかかる手続きはどれなのでしょうか?
文字で読むより、
スパッと答えが欲しい!
というあなたは…
会社設立についてのお問い合わせは、
こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。
会社設立手続きのうちお金が必要なのは?

さきほど説明した手続きのうちお金がかかる手続きは、大きくこの4項目と考えてください(自分ですべてやる場合)。
- 定款の認証手数料、定款に貼る収入印紙代(※)
- 登録免許税(法人設立)
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の発行手数料
- 印鑑作成代、交通費
※電子定款を利用した場合は、定款に貼る収入印紙代は不要になります。実際、会社を作るにはこれだけの費用がかかります。
それでは、会社設立の費用について、「自分ですべて進める場合」と、「司法書士さんに依頼する場合」にわけて説明していきますね。
会社設立費用(一人で手続きをする場合)

「会社を退職日も決まり、そろそろ会社を設立したいと思っています。」田中誠さん(仮名)は、現在は会社員ですが、13年勤めた会社を辞めて独立することが決まっています。
今日は●年8月22日。退職日はきりのいい8月31日。退職日の翌日である9月1日には株式会社を立ち上げて、今までやってきた経営コンサルティングを今度は会社の社長として運営していくことになっています。
誠さんの夢はすでに大きく膨らんでいます。
誠さんは、今日も1日中インターネットの記事や本を読んでいました。
一通り、会社の設立にかかる費用について調べましたがどれもよく分からない、という状況でした。
まずは自分でやってみようと思い、「設立手続きの一覧」を参考に一つずつやってみることにしました。

※設立手続きの一覧は、この記事の上部にあります。
- 8月22日(火) ネットで会社の印鑑を発注
- 8月24日(木) 会社の印鑑が到着
- 8月25日(金) 近所のコンビニで個人の印鑑証明書を取得
- 8月26日(土) 自分で定款を作成、郵便局で収入印紙を購入
- 8月28日(月) 公証役場に行って定款の認証を受けた
- 8月29日(火) 登記申請書の作成
- 9月1日(金) 法務局に行って登記申請書の提出
- 9月8日(金) 再度法務局に行って登記簿謄本と印鑑証明書を取得
上記のようなスケジュールに沿って、誠さんは手続きを進めていきました。
そして、かかったお金をまとめてみました。
すると…
- 印鑑の発注:3万円
- 収入印紙:4万円
- 公証役場で払う定款認証手数料:5万円(当日、現金払い)
- 定款の謄本交付手数料:約2,000円(250円×必要なページ数(めやすは、5通前後))
- 登記申請の際、登録免許税:15万円(法務局の収入印紙窓口で現金払い)
- 登記簿謄本等発行手数料:3,450円
- 公証役場、銀行、法務局への交通費(例):合計で1,920円
まとめると…
会社設立のための費用が合計で、27万7,370円かかりました。

払った日付と金額について
まとめると、下記の通りでした。
- 8月22日に3万円
- 8月28日に9万4,000円
- 9月1日に15万円
- 9月8日に3,450円
※交通費1,920円
それでは、この田中 誠さんの事例を踏まえて、会社設立費用一つひとつについて、【誰に】【いくら】【いつ】払うのかを解説していきます。
印鑑作成
※印鑑について詳しくまとめた記事は、
こちらにあります。
【誰に】
印鑑業者
【いくら】
相場を見てみると、
1.5万~3万円がおススメです
(高額なものはいくらでもありますが…)。
【いつ】
社名を決めたらすぐ発注するようにしてください。
※たまに印鑑を発注するとき、会社名を間違えて発注してしまう方がいますので、ご注意ください。
※角印について:最近は角印を使う場面は少ないので、角印だけは購入しなくても困ることはありません。
定款認証(ていかんにんしょう)
【誰に】
公証人役場の公証人
【いくら】
定款認証手数料 5万2千円
定款の謄本作成手数料 250円
× 必要なページ数
(めやすは、5通前後)
【いつ】
公証役場にて当日、現金で支払いを行います。
登録免許税(とうろくめんきょぜい)
【誰に】
法務局の印紙販売窓口
【いくら】
15万円 or 6万円
■株式会社の場合は、15万円と考えてください。
※計算式としては、資本金×0.7%ですが、最低金額が15万円となっています。つまり、資本金500万円であれば500万円×0.7%=3万5千円⇒最低15万円なので、15万円になります。
(資本金が2,200万円になると、15万円以上になります。)
■合同会社の場合は、6万円と考えてください。
※計算式としては、資本金×0.7%で、最低金額が6万円となっています。つまり、資本金500万円であれば
500万円×0.7%=3万5千円⇒ 最低6万円なので、6万円になります。
(資本金が859万円になると、6万円以上になります。)
※会社の種類
会社には「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4種類があります。
この4種類のうち「合名会社」「合資会社」を設立する人はほとんどいないため省略します。
また、昔は「有限会社」もありましたが、平成18年5月に廃止され、新たに作ることはできなくなったためこちらも省略します。
【いつ】
設立登記申請の当日
あなたが一人で会社設立をする場合でも、税金についてはなかなか分かりませんよね…
会社設立費用(司法書士に依頼する場合)

「会社を退職する日が近づいているので、急いで会社を設立したいんです!」
本間 勝治(かつじ)さん(仮名)は、現在は会社員。
20年勤めた会社を辞めて独立することが決まっています。
今は●年8月25日。退職日はきりのいい8月31日。
退職日の翌日である9月1日には株式会社を立ち上げたいと思っています。
とにかく時間がない。スピーディーに会社を設立したい、という状態でした。
また、手元資金も少ないため、できるだけ後払いにできたら、と考えていました。
そこで、インターネットで見つけた、会社設立の記事をたくさん書いている税理士さんに相談に行きました。
その税理士さんによると、税理士さんが提携している司法書士さんであれば、「スピーディーにやってくれますよ」とのことでした。
勝治さんは税理士さんが紹介してくれたその司法書士さんにすべてをお願いすることにしました。
- 8月25日(金) 依頼した司法書士からヒアリングを受け、その日のうちにネットで会社の印鑑を発注
- 8月27日(日) 会社の印鑑が到着
- 8月28日(月) 近所のコンビニで個人の印鑑証明書を取得
- 9月1日(金) 会社の設立日
- 9月8日(金) 司法書士から登記簿謄本などが郵送で送られてきました。
かかったお金をまとめてみると、
- 印鑑の発注:3万円
- 収入印紙:司法書士による電子認証のため、収入印紙は不要
- 司法書士に払う代行報酬:4万5,000円(司法書士報酬は自由化されているので、さらに下がることも。詳細はお問い合わせください。)
- 公証役場で払う定款認証手数料:5万円(後日、司法書士から請求)
- 定款の謄本交付手数料:約2,000円(250円×必要なページ数(めやすは、5通前後))
- 登記申請の際、登録免許税:15万円(後日、司法書士から請求)
- 登記簿謄本等発行手数料:3,450円(後日、司法書士から請求)
- 公証役場、銀行、法務局への交通費(例):合計で1,920円
会社設立のための費用が合計で28万2,370円かかりました。

支払った日付と金額は下記の通りでした。
- 8月25日に3万円
- 9月25日に252,450円を司法書士に振り込み
※交通費1,920円
司法書士さんに払う報酬の支払期限も気になりますよね。弊所の提携司法書士さんですと、月末締めの翌月末払いで対応してもらえます。
本間 勝治さんの事例を踏まえて、【誰に】【いくら】【いつ】払うのかを解説していきます。
印鑑作成(自分で手続きをする場合と同じ)
自分で手続きをする場合にも、
こちらの印鑑についての
記事を参考にしてください。
【誰に】
印鑑業者
【いくら】
相場を見てみると、
1.5万~3万円がおススメです
(高額なものはいくらでもありますが…)。
【いつ】
社名を決めたらすぐ発注するようにしてください。
※たまに印鑑を発注するとき、会社名を間違えて発注してしまう方がいますので、ご注意ください。
※角印について:最近は角印を使う場面は少ないので、角印だけは購入しなくても困ることはありません。
印鑑以外
【誰に】
司法書士に
【いくら】
- 司法書士報酬 4万5,000円
- 定款認証手数料 5万円
- (定款印紙代4万円)電子定款なら不要
- 定款の謄本交付手数料 2,000円前後
- 登録免許税 15万円(詳しくは上述の通り)
- 印鑑証明書手数料(1通450円)
- 司法書士が立て替えた交通費、郵便料金等の実費
合計で、約25万円
【いつ】
印鑑代は発注時または納品時。
司法書士への支払いは翌月末など(司法書士により異なります)
司法書士さんに依頼して会社を設立する場合の各項目についての詳細は…
設立前に支払った領収書を捨ててしまった…

会社設立前に支払ったお金なので事業に関係ないと思い、領収書を捨ててしまう方がときどきおられます。
例えば、事業に関係する人との飲食代、開業準備のための交通費、名刺代などです。
会社の設立前には、会社自体が世の中に存在しないので、会社が「支払う」こと自体、できません。
ただ、いったん個人で立て替えて、会社設立後に会社の経費にするということが税務上の認められているのです。会社設立前に支払った領収書は捨てないようにしてください。
※領収書の整理についてのご相談はこちらから
会社設立費用を節約しようとして…失敗事例も
「休眠会社を買い取ることで設立費用を節約したい!」
弊所のお客様で、こういう方がいました。
会社設立費用がもったいないからといって、知り合いが1年以上休眠にしていた株式会社を買い取りました。
ところがその会社は設立届も青色申告の申請も税務申告も、すべて無視していた会社でした。
しかも、会社名は前の会社のまま。結局、社名、代表者、本店所在地などの変更に15万円ほどのお金がかかってしまいました。設立時の届出をしていなかったことで白色申告になっていたため青色申告に戻すのに2年以上かかってしまいました。
このような、「会社を他人から譲り受ける」方法は、一見、会社設立費用の節約になると思いがちなのですが、たいして節約にもなりません。
しかも、場合によっては「隠れ債務」がある恐れもあるので非常にリスクが高い方法になります。このような事態に陥ってしまった方は、プロにお任せください。しっかりとご説明させていただきます。

このように、起業にはつきものの、「おいしい話」は基本的に断ってください。特にインターネットを中心に、会社設立がめちゃくちゃ安くできます!すべてゼロ円でできます!
というような甘い話が非常に多くなっています。もちろん起業にはコストを掛けたくないのも事実です。
でも、とりあえず「安く」会社ができればいいや…ではあとから後悔することになります。
※設立届の書き方についてはこちらの記事を、青色申告の申請については、こちらの記事を参考にしてください。
会社設立費用の勘定科目について

会社設立時に発生する費用は、適切な勘定科目で処理する必要があります。会社設立費用の主な勘定科目は「創立費」と「開業費」の2つに大別されます。
創立費
創立費とは、会社の法人格を取得するために直接必要となった費用のことを指します。具体的には以下のような費用が含まれます。
- 定款作成費用(公証人手数料を含む)
- 登録免許税
- 司法書士への報酬
- 印鑑証明書取得費用
- 設立登記申請費用
創立費は一般的に繰延資産として計上され、任意の期間(最長5年)で均等に償却することができます。なお、資本金が1億円以上の会社においては、創立費を支出時に全額費用として処理することも認められています。
開業費
開業費は、会社の事業を開始するために必要となった費用のことです。
創立費と異なり、法人格の取得とは直接関係しない費用が該当します。
- 事務所の内装工事費
- 備品・機器等の購入費
- 従業員の採用・研修費用
- 広告宣伝費
開業費も創立費と同様に繰延資産として扱われ、最長5年間で均等償却が可能です。
少額の場合の処理
会社設立費用の金額が少額である場合は、繰延資産として計上せずに、支出時に全額を費用として処理することも可能です。一般的には20万円未満の場合に認められることが多いですが、会社の経理規程や税理士の判断によって取り扱いが異なる場合があります。
消費税の取り扱い
会社設立費用に係る消費税は、設立後に消費税の課税事業者となる場合、一定の条件のもとで仕入税額控除の対象となります。ただし、設立1期目から免税事業者となる場合は、消費税分も含めて全額を創立費または開業費として処理します。
正確な処理方法については、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
適切な勘定科目での処理は、会社の財務状況を正確に表示するだけでなく、税務上のメリットを最大化するためにも重要です。
会社設立費用【まとめ】
会社設立費用について、
- 誰に
- いくら
- いつ
お金を払うのかについてその金額を具体的に示して説明をしました。
結論は、金額的にはあまり変わらないので、司令塔となってくれる税理士さんに司法書士さん、または行政書士さんを紹介してもらうのがベストです。
くれぐれも会社設立を「とりあえず」してしまった…ということのないようにしてくださいね。
起業で成功する人の共通点は「稼ぐのが早い」人です。会社設立で足踏みして稼ぐまでに時間がかかってしまった…とならないように注意してください。
同じように、起業のための資金が不足している場合はお金を借りてしまった方が稼ぐのが早くなります。
会社設立や起業のためのお金が足りない・・・という方は創業融資でお金を借りることもできます。
大阪で創業融資を受けるなら、大阪で創業融資サポートをしている税理士
に依頼する方が融資を受けやすいです。
※自分で申請するより有利になります。
会社設立費用は経費になるのか?
この記事で説明した「会社設立にかかる費用」は、
基本的にはすべて設立後の会社の経費になるので、その点は心配要りません。
会社設立前の費用を経費にできるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
この記事で触れていないことは、他にない?
この記事は、会社設立費用についてしっかりと理解していただき、準備をしていただくための記事です。
純粋に「会社を設立する」以外の内容、例えば税理士報酬や事務所家賃などには触れていません。
他にも、経営自体について気を付けることは業種によって様々です。その業種に関する専門家や先輩経営者に聞くのもいいかもしれませんね。
おススメの記事
「【会社設立】「資本金」が必要?どういうこと?!その意味を税理士が解説します!」
こちらの記事もこれから会社を設立する人に必須の知識ですので、ぜひ読んでみてください。
「会社設立を戦略から一緒に考える」税理士の大山俊郎でした。

大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導