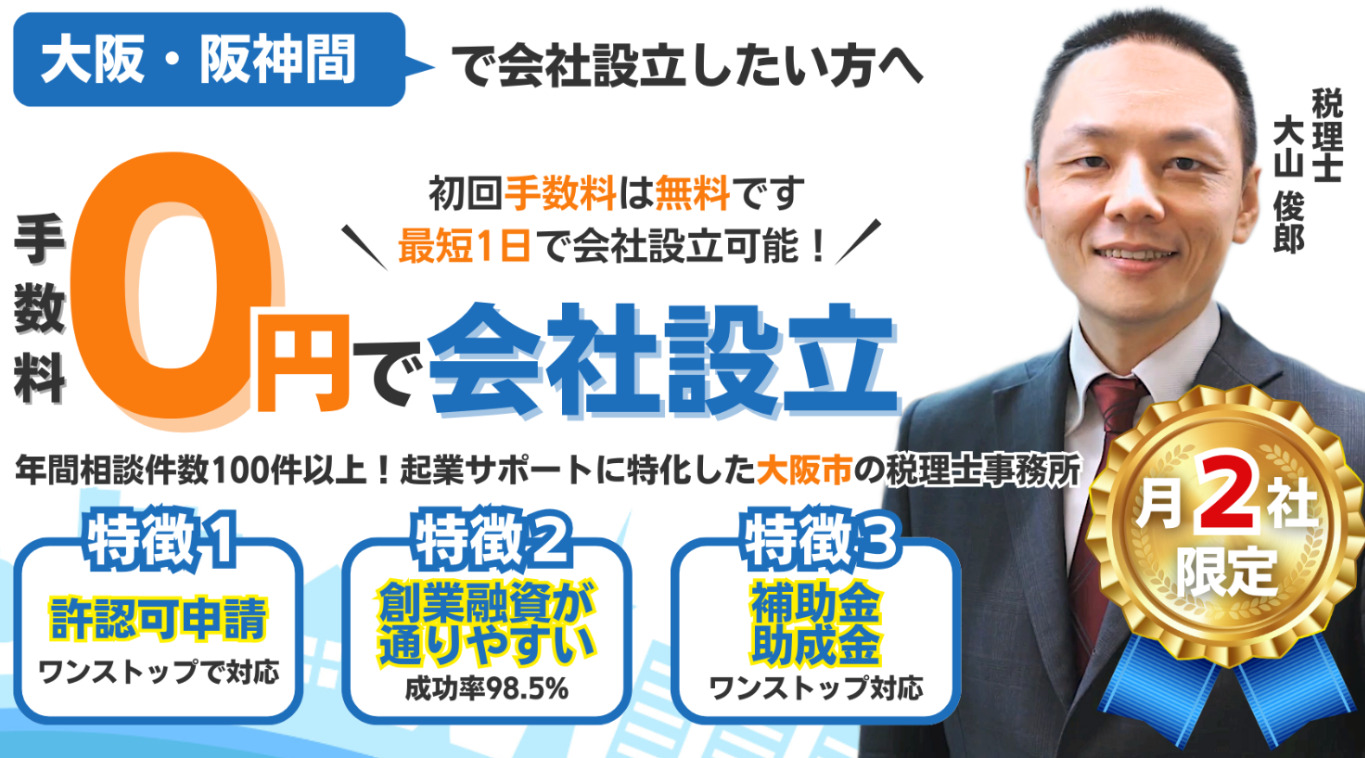源泉徴収(源泉所得税)とは?わかりやすく教えて!【税理士が初心者向けに解説】
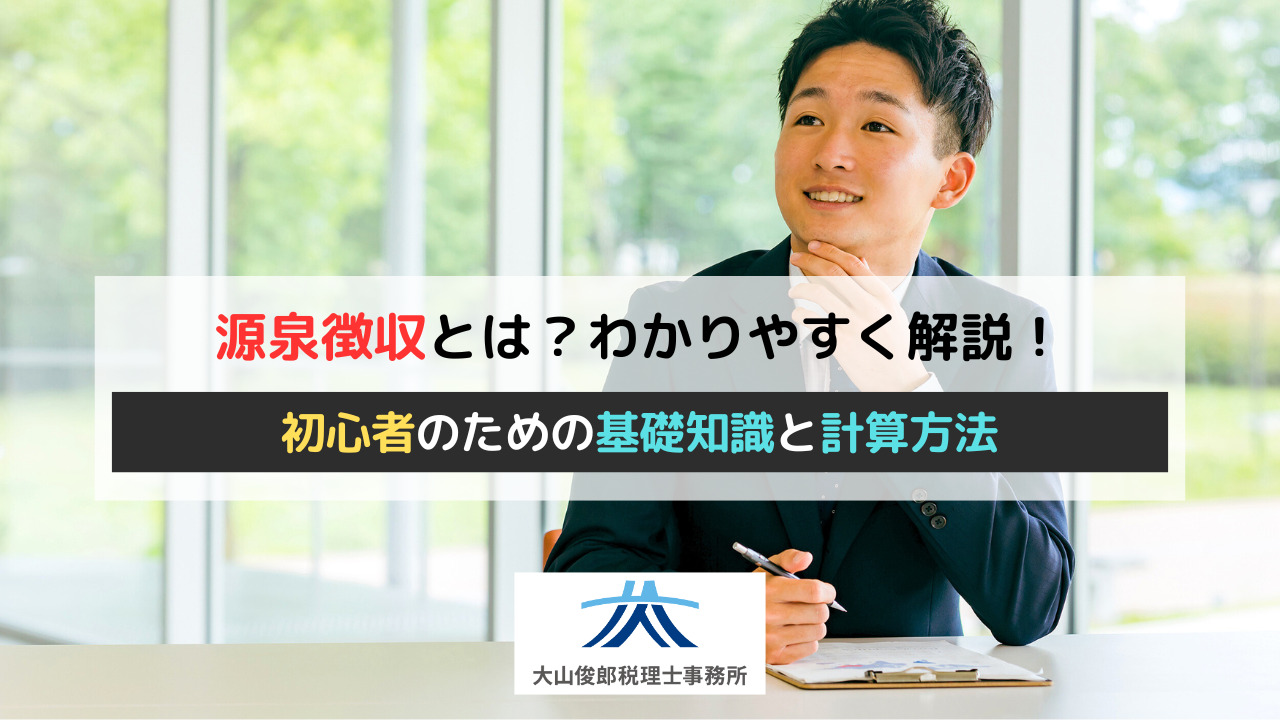
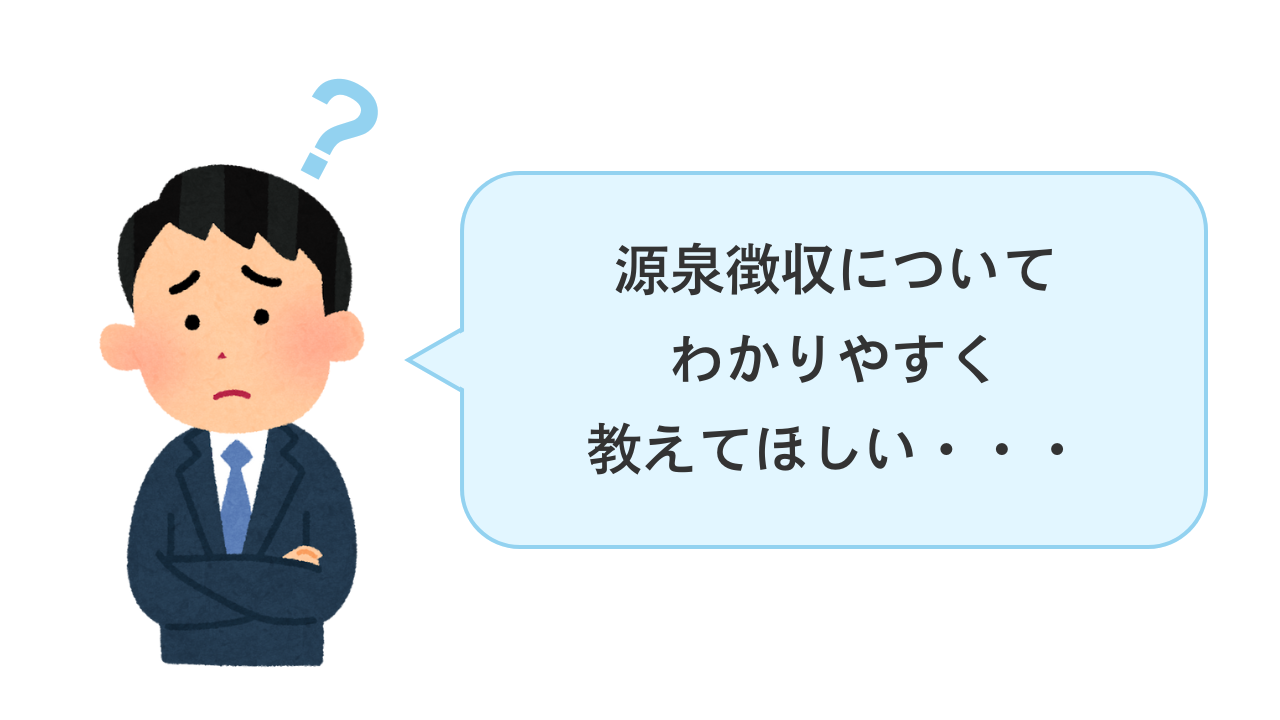 源泉徴収についてどのくらい知っていますか?
源泉徴収についてどのくらい知っていますか?
もしかしたら、「会社員の給与から引かれるあれでしょ?」という程度の理解かもしれません。
※源泉徴収に関連する用語には、「源泉所得税」「年末調整」「扶養控除」等、さまざまなものがあります。
源泉徴収は給与や報酬から源泉所得税を差し引いて納税する重要な制度です。
源泉徴収という制度のおかげで、従業員等は所得税を勤務先などから「先に天引きをしてもらう」ことで納税の手間が軽減されます。
所得税は1年間の所得に応じて確定申告で計算されますが、源泉徴収制度では給与や報酬を「受け取ったとき」に一定の金額を国(税務署)に納めるのが通常です。
※収めることを忘れないようにしましょう。
※所得税と源泉所得税の違い:所得税は納税者が支払い、源泉所得税は雇用主などが源泉徴収して納付します。
納税手続きを行うのは給与や報酬を支払う「会社または個人事業主」です。
また「源泉徴収票」は源泉徴収の詳細を説明するための重要な書類であり、源泉徴収の計算や算出のやり方を確認する際、確定申告の際にも役立ちます。
なお交付期限を過ぎると、給与や報酬を支払う「会社または個人事業主」が法律で罰せられる可能性があるため注意が必要です。
特に転職があった場合などは、前職の会社が発行した源泉徴収票を速やかに新しい職場に提出する必要があります。
この記事では、源泉徴収の基本的な仕組みや対象となる収入、源泉徴収票の見方、計算方法、扶養控除、確定申告の手続きについてわかりやすく解説します。
これにより、源泉徴収に関する理解が深まり、適切な対応ができるようになるでしょう。
源泉徴収制度について理解することで、年末調整や経理業務の効率化や法令遵守が図れるようになります。
特に、源泉徴収税額の計算方法や源泉徴収票の見方を知ることは、経営者にとっては重要です。
この記事を通じて、源泉徴収の仕組みをしっかりと学び、税務手続きを円滑に進めましょう!
✔ 源泉徴収とは何か、基本的な仕組みが知りたい
✔ 源泉徴収票の見方がわからない
✔ 源泉徴収の計算方法を知りたい
✔ 源泉徴収の対象となる収入と対象外の収入の違いがわからない
大阪で会社を作るなら、地元大阪の大山俊郎税理士事務所がサポートします!
大山俊郎税理士事務所は、大阪市営地下鉄谷町四丁目駅から徒歩3分。
\年間問い合わせ100件以上/
1. 源泉徴収とは何か?
まず概要を説明すると、源泉徴収は、給与や報酬などの支払い時にあらかじめ所得税を天引きし、支払者が税務署に納付する制度です。
これにより、納税者の税負担が軽減され、納税がスムーズに行われます。
法人経営者にとっては、従業員や取引先(特に個人)に対する支払い時に適切に対応することが重要です。
源泉徴収の基本的な仕組み
源泉徴収は支払者が給与や報酬から所得税を差し引き、税務署に納付する制度です。
これにより、納税者は一度に大きな税額を支払う負担が軽減され、税収が安定的に確保されます。
また、従業員やフリーランスの税務手続きが簡略化されるメリットもあります。
源泉徴収の対象となる収入
源泉徴収の対象となる収入には、給与所得、利子所得、配当所得、事業所得などがあります。
給与所得は、従業員への給与や賞与が該当します。
利子所得は銀行預金の利息、配当所得は株式の配当金が含まれます。
事業所得は、フリーランスや個人事業主の収入が該当します。
なお、「士業(弁護士・司法書士など)への報酬」や「株主への配当金」も源泉徴収の対象です。
また、日本国内に居住している人は、すべての所得が所得税の課税対象になります(この考え方を「全世界所得課税の原則」と言います)。
2. 源泉徴収の計算方法
源泉徴収の流れを5ステップで解説
「源泉徴収って具体的に何をするの?」と迷う方も多いはずです。
ここでは、給与の源泉徴収がどのような流れで行われるのか、実務担当者の視点で5つのステップに分けて解説します。
【STEP1】 扶養控除申告書を確認する
給与から差し引く源泉所得税の金額は、「扶養控除等(異動)申告書」の有無や内容によって変わります。
まずは従業員が提出しているか、扶養親族数に間違いがないかを一定期間ごとにチェックしましょう。
実務ポイント:
-
新入社員や毎年1月には必ず「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう。
-
扶養親族の人数と本人情報の記入ミスがないかを確認。
ミスしやすい点:
-
書類の未提出(提出がない場合は「乙欄」適用で税額が高くなる)
-
扶養人数の記載ミスや、途中で家族構成が変わったのに申告書が更新されていない
事例:
例:4月入社のAさんが申告書を提出していなかったため、給与計算で「乙欄」を適用。結果として本来より高い所得税が天引きされていた。Aさんが申告書を出していれば「甲欄」で計算でき、手取りが増えたはず。
【STEP2】 社会保険料を差し引く
毎月の給与から健康保険や厚生年金などの社会保険料を差し引きます。
ここを間違うと課税額が変わるので要注意です。
実務ポイント:
-
健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料など、控除すべき保険料を正確に差し引く
-
控除後の「課税対象額(=課税給与)」を出す
ミスしやすい点:
-
保険料率の変更や、保険料の引き忘れ
-
住民税や労働保険と間違えてしまう
事例:
例:毎年4月や9月は保険料率が変更されやすい時期。前年の料率で計算し続けてしまい、従業員から「控除額が違う」と指摘を受けたケースも。
【STEP3】 源泉徴収税額を調べる
国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」を使い、法律の定めにより、正しい税額を確認します。
税額表は“前年”のものを使っていませんか?」「納付期限は“翌月10日”を絶対に忘れずに!
税額表は毎年変わるため、必ず最新版を使いましょう。
実務ポイント:
-
国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を必ず最新版で使う
-
甲欄・乙欄の使い分けを間違えない
-
税額表の「支給額」のどの欄を使うか確認
ミスしやすい点:
-
去年の税額表を使い続ける
-
甲欄・乙欄の選択ミス
-
支給額を控除前の金額で見てしまう
事例:
例:扶養控除申告書を提出しているBさん(甲欄)、月収25万円、社会保険料引き後の課税額23万円。
税額表「甲欄」23万円の行を確認→その金額が源泉徴収税額。
【STEP4】 所得税を天引き・納付
計算した所得税を給与から差し引き、翌月10日までに税務署へ納付します。
納付には「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」を使います。
実務ポイント:
-
毎月10日までに「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」で納付
-
納付額・対象者数・支給総額を記載ミスしない
ミスしやすい点:
-
納付期日を忘れる(特に祝日が絡む月に注意)
-
納付額や記載内容の転記ミス
事例:
例:6月10日が日曜日の場合、納付期限は翌営業日の6月11日(月)に延長される。期限を間違えると延滞税が発生するので注意。
【STEP5】 年末調整で精算
1年の終わりに「年末調整」を行い、これまで天引きしていた所得税が本当に正しかったかを精算(最終的に調整)します。
過不足があれば還付や追加徴収が行われます。
実務ポイント:
-
12月支給分(または退職時)に年末調整を実施
-
保険料控除申告書など追加の書類をもとに再計算
ミスしやすい点:
-
途中入社・退社の人や、2か所給与がある人の調整漏れ
-
保険料控除証明書や住宅ローン控除書類の提出漏れ
事例:
例:Cさんが年の途中で生命保険に加入し、保険料控除証明書を年末調整に提出。これにより所得税の過払い分が還付された。
※給与計算を誤ると「社会保険料」にも影響が出るので注意してください。
給与所得の源泉徴収計算
給与所得の源泉徴収計算は、支給する給与額に基づいて行います。
まず、支給額から社会保険料などの控除を差し引き、課税対象額を求めます。
次に、税率表を基に所得税額を計算し、その額を給与から差し引いて税務署に納付します。
具体的な例として、月額給与が30万円の場合、控除後の課税対象額に対する税率を適用して計算します。
事業所得の源泉徴収計算
事業所得の源泉徴収計算は、主にフリーランスや個人事業主に対する報酬が対象です。
報酬額に一定の税率を適用し、所得税額を差し引きます。
例えば、報酬額が10万円の場合、10.21%の税率を適用して計算し、所得税額を求めます。
この額を報酬から差し引いて税務署に納付します。
3. 源泉徴収の納期の特例とは?
源泉徴収した所得税は、原則として「支払月の翌月10日まで」に税務署へ納付する必要があります。
しかし、中小企業や従業員数が少ない事業者などの場合、毎月納付の手間を軽減するために「納期の特例」という制度が設けられています。
納期の特例とは、原則として「支払月の翌月10日までに」というルールとは異なり、一定の要件を満たす事業者だけが、源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納付できる制度です。
通常は毎月納付が必要ですが、この特例を利用すると1月から6月分を7月10日まで、7月から12月分を翌年1月20日までに納付すればよくなります。
年に2回だけになることで忘れやすくなるので注意してくださいね。
納期の特例の対象となる事業者
納期の特例を利用できるのは、常時雇用する従業員が10人未満の事業者など、一定の要件を満たす場合です。
利用するためには、あらかじめ所轄税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
【ポイント】
-
特例を適用していても、納付が遅れると延滞税等のペナルティが発生するので注意しましょう。
-
賞与や退職金などの特別な支払いも原則は特例の対象ですが、例外もあるため、詳細は国税庁のガイドライン等を確認しましょう。
納期の特例のメリット
-
毎月納付の手間が減るため、事務負担を軽減できる
-
小規模事業者でも無理なく源泉徴収税の納付ができる
この制度を活用することで、事業運営の効率化と納税の確実性を両立できます。
なお、手続きや条件が変更されることもあるため専門家を利用することも考えておきましょう。
4. 法人経営者が知っておくべきポイント
法人経営者は、源泉徴収に関する義務を理解し、適切に対応することが求められます。
また、税理士を活用することで、源泉徴収に関する手続きをスムーズに進めることができます。
以下に、法人経営者が知っておくべきポイントを解説します。
法人の源泉徴収義務
法人は、従業員や取引先に対する給与や報酬の支払い時に、所得税を源泉徴収する義務があります。
国税庁のガイドラインも参照しましょう。
全体像をつかみたい場合は以下も参考になります。
この義務を怠ると、罰則やペナルティが課されることがあります。
適切な源泉徴収を行うためには、最新の税率表や法規制を常に確認し、従業員や取引先に対する支払い時に正確に対応する必要があります。
税理士の役割
税理士は、法人経営者が源泉徴収に関する手続きを正確に行うためのサポートを提供します。
税理士に依頼することで、源泉徴収の計算や納付手続きがスムーズに進み、法令違反を防ぐことができます。
また、税理士は最新の税法や規制に精通しており、経営者が必要な情報を迅速に得ることができます。
5. 源泉徴収に関するよくある質問
源泉徴収に関しては、多くの疑問や質問が寄せられます。
以下に、よくある質問とその回答をまとめました。
法人経営者が源泉徴収に関する知識を深め、適切に対応するための参考にしてください。
給与以外の収入に対する源泉徴収
給与以外の収入に対する源泉徴収には、賞与や退職金が含まれます。
賞与の場合、支給額に応じて異なる税率が適用されるため、適切な計算が必要です。
退職金の場合も、特別な税率や控除が適用されるため、詳細な確認が求められます。
また、海外所得に対する源泉徴収についても、各国の税法や協定に基づいて対応する必要があります。
源泉徴収の還付手続き
源泉徴収の還付が必要な場合、正しい手続きを踏むことで還付を受けることができます。
還付手続きには、必要な書類の提出や、税務署への申請が含まれます。
まず、源泉徴収票や還付申告書を準備し、適切に記入します。
次に、税務署に提出し、審査を経て還付が行われます。
法人経営者は、従業員や取引先に対する還付手続きを適切にサポートすることが求められます。
経営コンサルタントにコンサルタント料を支払うのですが、源泉徴収は必要ですか?
必要です。
6. まとめ
ここまでのポイントをまとめます。
- 源泉徴収は給与や報酬支払い時に所得税を天引きする制度
- 源泉徴収は給与、利子、配当、事業所得が対象
- 給与所得の源泉徴収は支給額から控除を差し引いて計算
- 法人は源泉徴収義務を負い、違反時には罰則がある
- 税理士は源泉徴収の計算や納付手続きをサポートする
源泉徴収についての基本的な仕組みや計算方法、法人経営者が知っておくべきポイントを詳しく解説しました。
源泉徴収制度を理解し、正しく対応することは、消費税など他の税務手続きにも役立ちます。
税理士など専門家と連携し、各種税金の違いと納付時期を把握することが、法人経営の安定につながります。
源泉徴収は、給与や報酬支払い時に所得税を天引きし、納税者の負担を軽減する重要な制度です。
法人は源泉徴収の義務を負い、違反時には罰則があるため、正確な対応が求められます。
以上のように給与計算は、経理業務のなかでも特に高度な専門性と精度が求められる領域です。
源泉所得税や社会保険料を一円単位まで正確に反映させることは、会社の法令遵守と従業員の安心を守るうえで欠かせません。
わずかな計算ミスでも税金・保険料の過不足や行政への納付額の相違につながり、企業の信用リスクを高めてしまいます。
大山俊郎税理士事務所では、源泉徴収税額の算定を含む毎月の給与計算、給与明細の発行・郵送までをワンストップで代行。
最新の税制改正を常にキャッチアップし、正確・迅速・機密保持を徹底しています。
給与計算を専門家にアウトソースすることで、経営者の皆さまは本業に集中しつつ、税務・社会保険に関するリスクを大幅に軽減できます。
「自社での給与計算に不安がある」「より効率的にバックオフィスを整えたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
初回相談は無料です。
電話でもお申し込みOK
06-6940-0807
【受付時間】10:00〜18:00(土日祝除く)

大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導