なぜ納付書が届かないのか?中間(予定)納税の新ルールと今すぐできる3つの対策【税理士が解説】
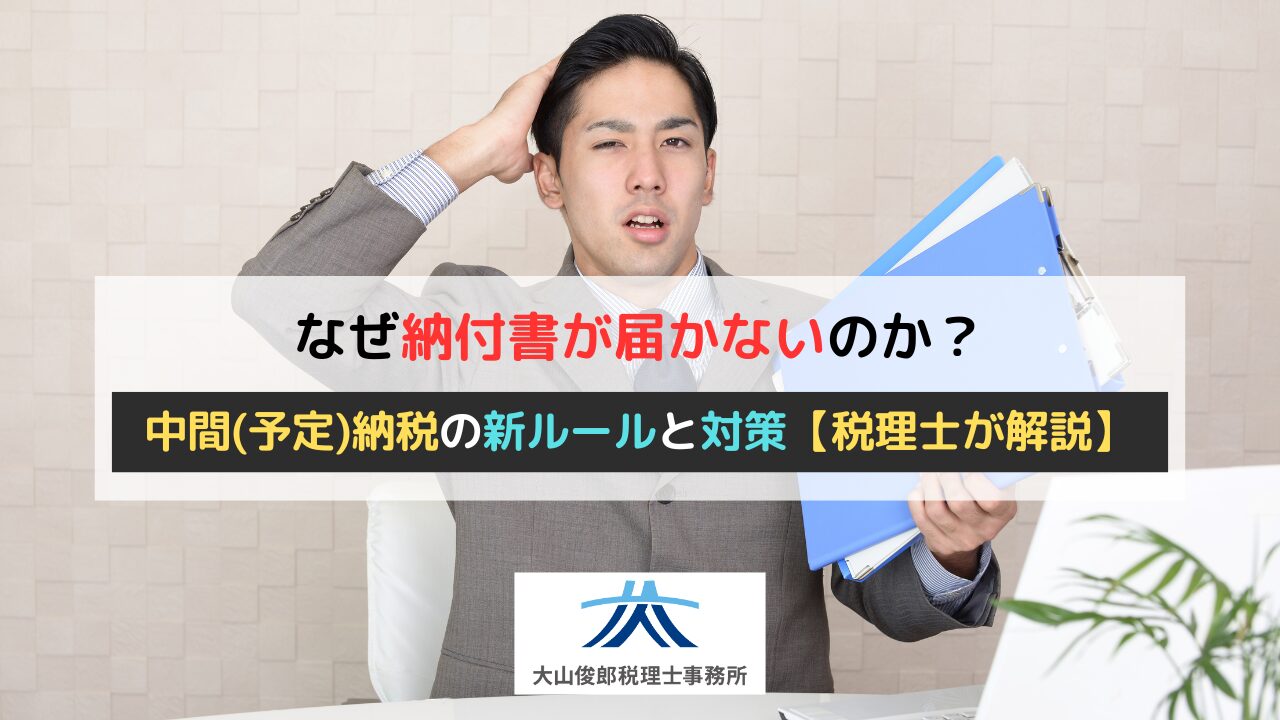 「知らなかった」では済まされない経営判断とお金の話
「知らなかった」では済まされない経営判断とお金の話
(※国税庁公式発表と、現場支援からの実感を交えて)
2024年(令和6年)5月分以降、法人税や消費税の中間(予定)納税について、納付書が税務署から届かないケースが一気に増えています。
「うちにも何も届いてないけど大丈夫?」と相談を受けることが増えましたが、
これは決して個別のトラブルではなく、国税庁が公式に「納付書の事前送付をやめる」と明言しているからです。
国税庁公式発表より
「納付書を使用しない納付手段で納付した方などについては、納付書の事前の送付を取りやめております。」
経営現場で今、実際に起きていること
例えば年商1億~10億円規模の企業を率いる二代目社長・田中さん。
彼は、銀行融資に頼りすぎることへの葛藤や、資金繰りの漠然とした不安に常に頭を悩ませてきました。
「納付書が来ないから、納税もつい後回しに…」
その油断が資金ショートにつながりかねないことを、日々現場で目の当たりにしています。
どんな会社が納付書を受け取れなくなるのか?
国税庁の発表をまとめると、
e-Taxで申告している会社や、ネットバンキング・口座振替等で納付している場合、事前送付はストップされます。
-
e-Taxで申告書提出の法人
-
e-Tax義務化法人
-
e-Taxで通知書のみ希望した個人
-
ダイレクト納付(e-Tax口座振替)
-
振替納税
-
インターネットバンキング
-
クレジットカード・スマホアプリ納付
-
コンビニ(QRコード)
従来どおり「紙の納付書でしか納付しない方」は、今も納付書が届きます。
消費税の中間納付書は“今は”届く…でも注意!
消費税中間申告分の申告書及び納付書については、e-Tax義務化法人を除き、当分の間、引き続き送付することとしています。
つまり、法人税の予定申告分は基本届かないが、消費税の中間申告・納付書は(義務化法人除き)“当面は”届きます。
「今は届くから大丈夫」と安心せず、将来的な完全電子化も視野に「納税の管理を自社主導で」行う習慣が必要です。
資金繰り現場で“起きがち”なミス
「納付書が来ない→納税を忘れる→延滞税や資金ショート」
このパターンは本当に現場でよく見ます。
「決算賞与や設備投資の資金計画は頑張って立てているのに、納税資金の確保をうっかり抜かす」というのは、多くの社長にとってよくある悩みです。
なぜ、こうした失敗が多発するのか?
多くの経営者が、「納付書が来たら払えば大丈夫」と“受け身の資金管理”に慣れてしまっているからです。
実はこの“スタンス”こそが、利益が出ているのにお金が残らない最大の原因になり得ます。
(実例:自社のキャッシュフロー表や納税カレンダーを“見える化”しただけで、資金繰りの改善が一気に進んだお客様も多数います。)
専門家の現場から伝えたいこと
AIやマニュアル的な税務支援ではなく、経営者目線で一緒に数字と向き合うことで、
「資金繰りの不安」や「うっかり納税忘れ」を根本から防げる──
これは、現場で200社以上支援してきた中で確信していることです。
経営者自身が「お金の動きを主導」する時代へ
納税を“税理士任せ・役所任せ”にせず、
・カレンダーやスマホで納税日をリマインド
・月1回は資金繰り表で“納税予定額”を確認
・e-Taxメッセージボックスに必ず目を通す
この“ちょっとした習慣”が、会社の命綱を守ります。
最後に──当事務所のサポート
「数字が苦手な社長でも、資金繰りの見える化で未来が変わる」
納付書が届かない時代、
納税漏れや資金ショートを「たまたま運良く避ける」のではなく、
“自分で選び、コントロールできる”経営に変えませんか?
納税手続きや資金繰りの不安、「何から変えればいい?」という疑問もどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
国税庁最新情報と現場の両方からサポートいたします。
※「納付書、届かないまま放置してた…」というご相談が増えています。
✅ 納税タイミングや金額の確認をご希望の方は、
👉 こちらをクリックしてフォームへお進みいただき、
「お問い合わせの内容」欄に、以下の番号をご記入ください。① 納付書が届くかどうか不安
② 次の納税日・金額が不明
③ e-Tax関連の通知の確認方法を知りたい
④ その他(具体的にご記入ください)
無理な相談ではなく、確認サポートだけでも対応していますので、お気軽にどうぞ✉️

大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導
