インボイス制度は建設業に影響を与える?制度についてもわかりやすく解説!
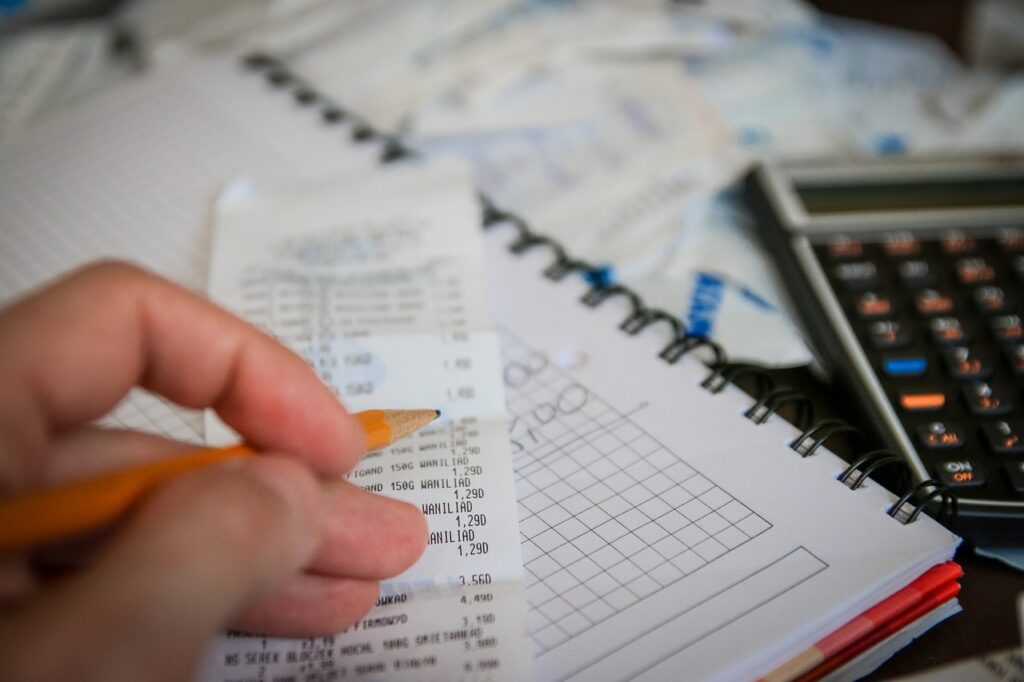
インボイス制度とは、売り手が買い手に正確な税率を正しく伝えるために新しく定められた、消費税のルールです。
2023年10月より本格運用が開始されますが、導入にあたっては課税事業者・免税事業者に関係なく多くの事業者に影響があります。
この記事では、事業の中でも「建設業」に注目して、インボイス制度が与える影響について解説していきます。
【建設業者必見】インボイス制度をわかりやすく解説!

まずはインボイス制度について詳しくみていきましょう。
インボイス制度が導入された背景
2019年10月より軽減税率制度の実施に伴って、消費税が「標準税率10%」と「軽減税率8%」の2種類になりました。
種類が増えたことで取引金額だけでは税額を正確に判断することが難しくなり、適正な税率を区分するためにインボイス制度が導入されたのです。
軽減税率8%の対象になる品目は飲食料品や新聞等が対象のため、建設業にはあまり影響はないかもしれません。しかしインボイス制度は、消費税に関わるルール変更なので、建設業もまったく関係ないとはいえないのです。
インボイス制度の仕組み
インボイスの正式名称は「適格請求書」といい、指定された項目が記載された書類が該当します。
そして適格請求書を発行できるのは、事前に登録申請をした「適格請求書発行事業者」のみです。
消費税は「売上の消費税額ー仕入れの消費税額」を引いた税額を納めており、この仕組みを仕入税額控除といいます。
これまで仕入税額控除は、納税義務のあるすべての企業に適用されていました。しかしインボイス制度が導入されると「適格請求書発行事業者」から発行された、適格請求書に記載の税額しか仕入税額控除の対象にならなくなるのです。
建設業も例外はなく、適格請求書に記載の税額しか仕入税額控除の対象にならないのですが、適格請求書発行事業者になれる事業者には決まりがあります。
対象にならない事業は申請登録ができないため、適格請求書の発行ができないことから発注者及び下請け業者は取引や利益を脅かす恐れがあるのです。
インボイス制度の対象になる事業者
インボイスに登録できるのは課税事業者のみです。ゆえに課税売上が1,000万円以下の免税事業がインボイス制度に登録するには、課税事業者に転換する必要があります。
建設業にも免税事業者や一人親方がいるので、課税事業者に転換するかそのまま事業を続けるのか選択が迫られるでしょう。
課税事業者になると適格請求書が発行できるので、今後の取引や事業への影響は少ない一方で、納税の義務が発生するので負担が大きくなる可能性が考えらえます。
免税事業者や一人親方は申請登録するメリットとデメリットを十分に把握したうえで、検討することが大切です。
インボイス制度によって建設業界は変わる?

インボイス制度導入によって、建設業はどのように変わるのかみていきましょう。
インボイス制度が及ぼす建設業への影響
インボイス制度が本格運用されると、適格請求書発行事業者から発行された帳票でなければ仕入税額控除を受けられません。
したがってこれまで材料や外注していた企業が適格請求書発行事業者かどうか、事前に確認しておく必要があるでしょう。
免税事業者との取引はコストがかかる
免税事業者から発行された請求書などでは仕入税額控除を受けられないので、納付する消費税額の負担が増えます。
インボイス制度の導入後は免税事業者との取引が多いと、企業にとって利益が減る可能性もあることを考慮しておきましょう。
偽装請負問題が少なくなる
偽装請負問題とは社会保険料や福利厚生費、手当ての費用を削減する目的で、従業員を会社から独立させて請負契約の形で仕事をしてもらうことをいいます。
インボイス制度が導入されると免税事業者は仕事が減るリスクがあるので、偽装請負状態が少なくなると考えられています。
免税事業者や一人親方は仕事が減る可能性がある
課税事業者にとって免税事業者との取引は、仕入税額控除が適用されないという点から懸念される可能性が高いです。
企業にとって納付額はできるだけ少なくしたいもの。しかしインボイス制度導入後に免税事業者との取引が多くなると、課税事業者の負担が増えてしまいます。
ゆえに免税事業者は、課税事業者との仕事が減少する恐れがあるのです。
請求書から適格請求書へと変わる
インボイス制度が導入されると、これまでの請求書の内容に加えて以下の事項を記載する必要があります。
・適格請求書発行の法人名または氏名及び登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率対象の品目であるか明確にする)
・税率ごとの合計額と適用税率
・税率ごとの消費税額
・適格請求書を受領する法人名または氏名
必要項目が記載されていないと適格請求書としてみなされないことがあるのでご注意ください。
建設業におけるインボイス制度導入が必要な理由

ここでは、建設業にとってインボイス制度がどうして必要なのかをみていきます。
インボイス制度導入の必要性
インボイス制度を導入する大きな目的は主に以下の3つです。
①消費税額を正確に把握すること
②消費税に関するミスや不正を防ぐこと
③益税の排除
企業が税務署に消費税を納付するとき「売上に係る消費税額ー仕入れに係る消費税額」で納付額が決まります。しかしインボイス制度では税率ごとに消費税を計算する必要があり、さらに計算根拠となった請求書等の帳票を保管しておくことで、正当性を持たせられるのです。
また建設業者がお客様から工事を受けた際に、免税事業者に仕事を依頼したケースの場合。免税事業者は納税の義務がないので、発注側より支払われた消費税がそのまま手元に残ってしまいます。
この残った消費税を「益税」といいます。インボイス制度導入によって免税事業者が課税事業者に転じることが増え、結果として益税の抑制に繋がると考えられているのです。
こういった理由から、インボイス制度の導入が進められてきました。
インボイス制度導入のメリット
次にインボイス制度を導入する主なメリットは次の2つです。
①電子インボイス導入のきっかけになる
②保管スペースの削減
インボイス制度がはじまることによって、電子インボイスの導入がしやすくなります。電子インボイスとは電子データによって受領した適格請求書のこと。
ただし電子インボイスの保管には電子帳簿保存法を遵守する必要があります。電子帳簿保存法について詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
また電子データでの保管が可能になることで、ペーパーレス化を推進できるようになります。今まで書類を印刷してファイルに保管していた作業がパソコンひとつで完了するので、保管スペースの削減に繋がるでしょう。
インボイス制度を導入するときの注意点

ここでは、インボイス制度を導入する時に注意すべきことについてみていきましょう。
インボイス制度への事前登録が必要
2023年10月からの本格運用に合わせてインボイス制度の適用を受けるには、事前に登録申請が必要です。
申請には登録申請書を郵送する方法と、e-Taxで電子申請する方法があります。登録が完了すると「適格請求書発行事業者の登録通知書」が届くので保管しておきましょう。
必要なシステム導入や業務フローの見直し
適格請求書には記載すべき事項の決まりがあります。ゆえに小売業や飲食店ではレシートに印字するためのシステム導入が必要になるケースもあるでしょう。
また経理では業務を効率化させるために電子化を進めた場合、業務フローの見直しが不可欠になります。ゆえに最初は混乱を防ぐためにも、早めに新しい業務フローの周知徹底をおこなうようにしましょう。
インボイス制度の正しい知識を身につける
インボイス制度では経理業務の仕訳が変更になります。
現在の消費税の端数処理は、品目ごとに計算をおこないその都度端数してもいいことになっています。しかしインボイス制度ではルールが異なり、税率ごとに合計金額を出してから消費税の計算をしなければなりません。つまり税率ごとに1回の端数処理しかできないということです。
このように日々業務や申告など経理業務が今までと変更になる個所があるので、正しい知識を身につけることが大事です。
協力業者が適格請求書発行事業者か確認する
インボイス制度に登録している事業者は、免税事業者との取引が多いと納税額の負担が多くなってしまいます。
そのため課税事業者との取引を希望する場合には、協力業者が適格請求書発行事業者かどうか確認しておくのが良いでしょう。
建設業法などに抵触しないように注意
インボイス制度導入によって課税事業者は、納税額の負担を増やさないために免税事業者との取引を減らしたり終了させることが考えられます。
また免税事業者と取引を続ける場合も、発注者が補う納税額を補おうと契約金額を調整するケースもあるでしょう。
しかし免税事業者は交渉の場において不利な立場にあることを利用して、条件取引をしてしまっては建設業法などに違反になることもあるので注意が必要です。
建設業のインボイス制度への対処法

建設業におけるインボイス制度に対する対処法は「発注側」と「受注側」で異なります。
それぞれみていきましょう。
発注者側の対応方法
インボイス制度導入によって、発注者側の対策は主に以下のものが考えられます。
- 発注者側で納税の負担することを了承して、免税事業者のまま取引する
- 納税額の負担が増えた分を、免税事業者から差し引いて相殺する
- 一人親方だった場合には、自社の職員として雇い入れる
- 課税事業者になることを促す
必ずしも納税額が増えるからといって取引を辞める必要はありません。協力業者と相談のうえ、上記の対策を参考に最善の選択をしましょう。
受注側の対応方法
受注側の対策方法は次のものが考えられます。
- 納税額を負担してもらうことに了承を得て免税事業者のまま事業を続ける
- 課税事業者との取引が多い場合は、課税事業者になることも検討する
- 取引先が免税事業者の場合はインボイス制度は関係ない
受注側は取引先が課税事業者だった場合、事業継続に影響がでるかもしれません。取引先に相談のうえ、インボイス制度の導入を検討しましょう。
インボイス制度を把握して導入を検討しよう
建設業でのインボイス制度導入による影響は大きく、早めの対策が必要です。ただし「発注側」と「受注側」では検討すべき事項が異なります。
免税事業者は課税事業者に転じるか、また課税事業者は下請け業者に免税事業者が多い場合、納税額を負担するか新しい下請け業者を探すなどの対応を進める必要があるでしょう。
インボイス制度導入までに制度の概要の理解や登録申請の方法、業務フローの見直しなど準備を進めていきましょう。
電話でもお申し込みOK
06-6940-0807
【受付時間】10:00〜18:00(土日祝除く)

大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導





