【事前確定届出給与】たった1日のズレで経費にならない?─役員賞与の届出期限を読み違えた会社の代償
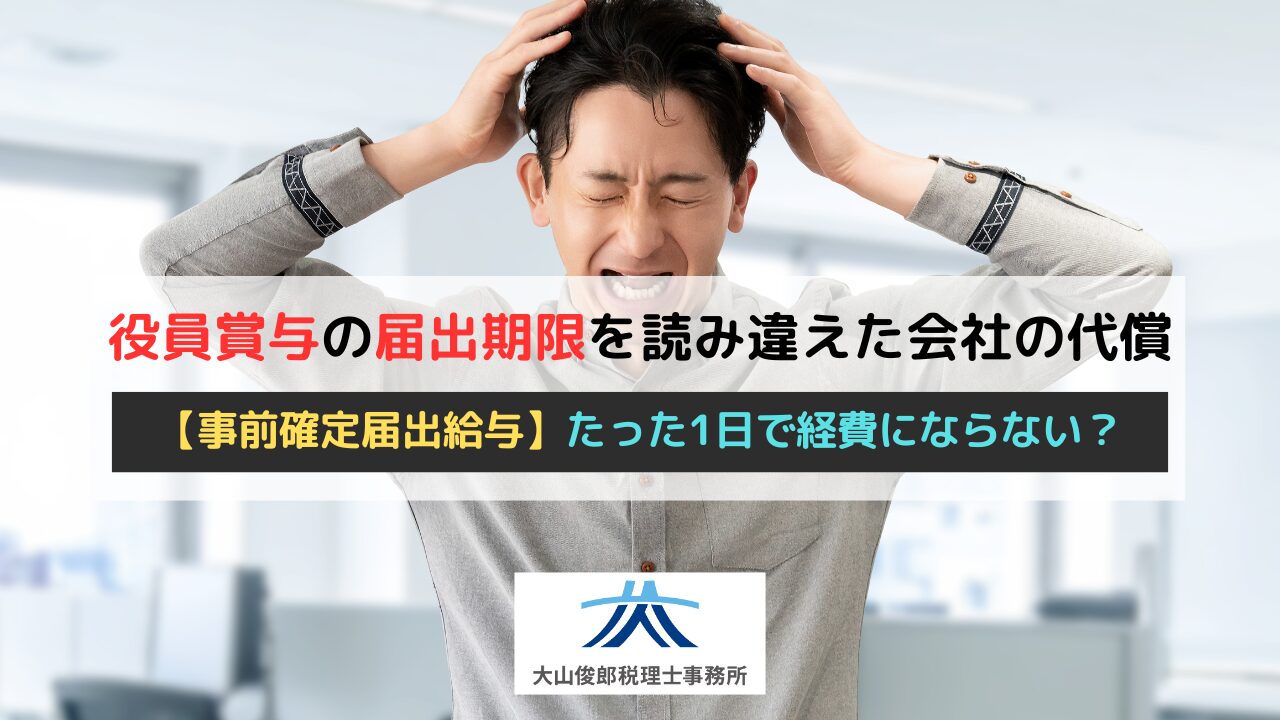
税理士にとって「期日」は特別な言葉
税理士として長く働いていると、「期日」という単語に妙に敏感になっていくのを感じます。
なぜなら、お客様の申告期限を1日でも間違えれば、それだけで信頼を失う仕事だからです。
期限を守ることは、税理士の信用そのものと言っても過言ではありません。
「事前確定届出給与」の届出書に潜む落とし穴
税理士業務の中で、会社の役員賞与に関わる届出書 ― いわゆる「事前確定届出給与に係る届出書」を提出する機会があります。
書類の中身ももちろん重要ですが、実はそこに書く「日付」こそが、税理士泣かせのポイントなのです。
この届出書は、提出のタイミングを間違えると、会社の損益に大きな影響を及ぼしかねません。
それほど「期限管理」がシビアな書類です。
では、次のケースで正しい提出期限を導き出せるでしょうか?
<事例>
決算日:令和7年7月31日
② 職務執行の開始日:令和7年9月26日
③ ①または②のうち早い日から1か月を経過する日
④ 職務執行開始日を含む会計期間の開始日から4か月を経過する日
⑤ ③と④のうち早い日
この⑤が、届出書の提出期限にあたります。
「経過する日」っていつのこと?
①と②までは簡単ですが、③で多くの人がつまずきます。
まず、「①と②のうち早い日」を探します。
この例では、①の「9月25日」が早いですね。
次に、「1か月を経過する日」を求めます。
ここでの「経過する日」とは、期間がちょうど満了しようとしている日を意味します。
つまり、「まだ終わってはいないけれど、終わりの直前の日」。
したがって、この場合は10月25日となります。
一方で、「経過した日」と書かれていた場合は、「もう期間が過ぎた後の日」を指します。
この場合は10月26日が該当します。
④の計算と注意点
次に④を見てみましょう。
職務執行開始日(令和7年9月26日)が含まれる会計期間(令和7年8月1日〜令和8年7月31日)の開始日(令和7年8月1日)から4か月を経過する日を求めます。
結果は「令和7年12月1日」となります。
実は③の「10月25日」は誤り?
ここで注意したいのが、「国税通則法第10条」という法律です。
この法律では、期間の数え方について次のように定めています。
たとえば「9月25日から1か月を経過する日」を求める場合、
初日(9月25日)は含めず、その翌日(9月26日)を起算日とします。
そして、翌月同日(10月26日)の前日が「経過する日」となるのです。
つまり正解は「令和7年10月25日」となります。
年末の提出期限はどう扱われる?
一方、④の日付「12月1日」がもし休日に当たる場合、
税務署をはじめとした行政機関は、「行政機関の休日に関する法律」により、
12月29日から翌年1月3日まで休みと定められています。
このように休日と重なる場合、国税通則法第10条第2項で次のように規定されています。
「期限が日曜・祝日・その他の休日に当たるときは、その翌日を期限とみなす」
そのため、実際の提出期限は翌営業日(その年のカレンダーによる)となります。
正しい答えは?
最終的に、⑤に該当する正しい日付は
▶ 令和7年10月25日 です。
おわりに
普段何気なく扱っている「日付」ですが、税務の世界では1日の違いが大きな意味を持ちます。
税理士が「期日」という言葉に敏感になるのは、こうした法律上の厳密なルールを常に意識しているからなのです。
電話でもお申し込みOK
06-6940-0807
【受付時間】10:00〜18:00(土日祝除く)

大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導




