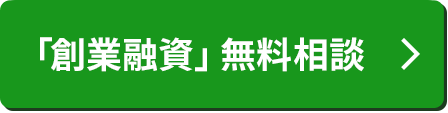創業融資で行政書士に相談すべきこと|店舗開業に必要な資金調達のポイントと専門家選び
 創業時の資金調達で悩んでいませんか?
創業時の資金調達で悩んでいませんか?
特に店舗開業には多額の資金が必要で、創業融資の申請に頭を抱えている方も多いでしょう。
「行政書士に相談すべきか、税理士がいいのか」
「創業融資の申請で行政書士はどこまでサポートしてくれるのか」
「行政書士への報酬はいくらかかるのか」
このような疑問を持っている方のために、この記事では創業融資における行政書士の役割と限界について徹底解説します。
結論からお伝えすると、行政書士は創業計画書などの申請書類作成に強みがありますが、店舗開業の資金調達では税理士のサポートも検討する価値があります。
日本政策金融公庫への融資申請において行政書士は重要なサポート役となりますが、融資の斡旋には貸金業または銀行代理業の登録が必要なため、単なる行政書士資格だけでは限界があることも理解しておくべきです。
実は、創業融資を成功させるためには「通る」だけでなく「必要な金額を借りる」という視点が重要で、そのためには書類作成だけでなく戦略的なアプローチが不可欠なのです。
この記事では、行政書士と税理士の業務範囲の違い、報酬体系の比較、創業計画書作成のポイント、そして記事の後半では日本政策金融公庫と銀行の併用融資戦略まで、創業融資の全体像をわかりやすく解説していきます。
店舗開業を目指すあなたが、最適な専門家を選び、理想の資金調達を実現するための情報をお届けします。
✔ 行政書士に依頼する際の報酬体系や費用相場が分からない
✔ 日本政策金融公庫の融資申請で重視されるポイントが知りたい
✔ 店舗開業に必要な資金をしっかり確保するためのコツを知りたい
創業融資と行政書士の役割を徹底解説
創業時の資金調達で悩んでいませんか?
多くの起業家が直面する創業融資の壁。
行政書士などの士業に依頼することで解決できる問題と、実際にどのようなサポートが受けられるのかを徹底解説します。
特に店舗開業に必要な資金計画のポイントをお伝えします。
創業時に必要な融資の種類と金額
創業時に必要な融資には、日本政策金融公庫の創業融資と銀行融資の2種類があります。
店舗型ビジネスの場合、物件費・内装費・設備費・人件費など多額の資金が必要になります。
例えば、飲食店なら1,000万円以上、美容室でも500万円以上が一般的な開業資金の目安です。
この金額を自己資金だけでまかなうのは難しいため、創業融資を活用することが現実的な選択となります。
日本政策金融公庫では最大7,200万円まで、銀行では担保や保証人の有無によって融資額が変わってきます。
重要なのは、「通る」だけでなく「必要な金額を借りる」という視点です。
妥協のない開業を実現するためには、物件・設備・人件費までカバーできる資金計画が不可欠です。
行政書士に依頼できる融資業務の範囲
行政書士に依頼できる融資業務には一定の範囲があります。
行政書士は主に申請書類の作成や提出代行が主な業務範囲となります。
具体的には、創業計画書の作成補助や各種申請書類の記入などが中心です。
ただし、行政書士は融資に関する戦略的なアドバイスや金融機関との交渉までは業務範囲に含まれないことが多いです。
つまり、書類作成のサポートは受けられますが、融資の全体戦略や金融機関対策までは期待できない場合があります。
実際に多くの起業家が「書類は整ったけど、面談でどう対応すればいいかわからない」という不安を抱えています。
理想的には、書類作成だけでなく面談対策や融資戦略まで含めたトータルサポートを受けられる専門家を選ぶことが重要です。
日本政策金融公庫の融資申請で重要なポイント
日本政策金融公庫の融資申請で最も重要なのは、具体的で説得力のある事業計画です。
公庫審査では、あなたの事業が「返済可能か」「継続性があるか」を重視します。
この2点を証明するために、市場分析・競合分析・収支計画を具体的な数字で示す必要があります。
特に収支計画では単に「こうなりたい」という希望的観測ではなく、「なぜその数字になるのか」という根拠が求められます。
例えば、飲食店なら客単価×回転率×営業日数といった具体的な計算式と、その数字の妥当性を示すことが大切です。
また、自己資金が少ない場合でも、しっかりとした事業計画と創業への熱意を伝えることで融資可能性は高まります。
公庫は創業支援を使命としているため、銀行よりも融資のハードルは低いと言えます。
創業計画書作成における行政書士のサポート
創業計画書の作成において、行政書士は専門的な知識と経験で大きなサポートとなります。
行政書士は多くの創業計画書作成に携わってきた経験から、審査担当者の視点を理解しています。
そのため、単なる数字の羅列ではなく、「なぜその事業か」「なぜあなたなのか」という点も含めた説得力のある計画書作成をサポートします。
具体的には以下のような点で役立ちます:
・適切なフォーマットの選択と記入方法の指導
・数値計画の妥当性チェック
・事業の強みや成長性の表現方法
・審査担当者が気にするポイントの解説
ただし、行政書士によってサポート内容や専門性には差があります。
特に店舗型ビジネスの場合は、その業種に精通した行政書士を選ぶことが重要です。
融資の「斡旋」には必要な資格があるのを知っていますか?
融資の斡旋を行うには、法律で定められた資格が必要です。
これは意外と知られていませんが、融資の斡旋を行うには「貸金業」または「銀行代理業」の登録が必要です。
行政書士や税理士の資格だけでは、融資の斡旋はできません。
「斡旋」とは、特定の金融機関を紹介して融資を受けさせる行為を指します。
ただし、一般的な情報提供や助言、書類作成サポートは「斡旋」には当たらないため、行政書士や税理士でも可能です。
このため、多くの専門家は「融資の紹介」ではなく「融資のサポート」という形でサービスを提供しています。
専門家に依頼する際は、どこまでのサポートを受けられるのか、事前に確認することが大切です。
店舗開業時の資金計画で失敗しないコツ
店舗開業時の資金計画で失敗しないためには、十分な余裕を持った計画が必要です。
多くの創業者が陥る失敗は、初期投資だけを考えて運転資金を十分に確保しないことです。
店舗ビジネスの場合、軌道に乗るまでの半年〜1年分の運転資金も含めた融資計画が必須です。
具体的には以下のポイントを押さえましょう:
・物件取得費だけでなく、内装・設備・備品などの初期投資を詳細に計算する
・人件費・仕入れ・広告費など月々のランニングコストを現実的に見積もる
・売上が安定するまでの運転資金(最低6ヶ月分)を確保する
・予想外の出費に備えた予備費(全体の10〜20%程度)を設定する
また、日本政策金融公庫と銀行融資を併用する「併用融資戦略」も効果的です。
公庫で設備資金、銀行で運転資金というように用途に応じて使い分けることで、必要十分な資金を確保できます。
創業融資成功のために行政書士と税理士の違いを知る
創業融資の申請において、行政書士と税理士のどちらに依頼すべきか迷うことがあります。
それぞれの専門分野や強みを理解することで、あなたの状況に最適な選択ができます。
特に店舗開業の場合は、資金計画の精度が重要になるため、慎重に専門家を選びましょう。
行政書士と税理士の業務範囲の違い
行政書士と税理士では、創業融資に関わる業務範囲に明確な違いがあります。
行政書士は主に「申請書類の作成」を得意としています。
創業融資に必要な各種書類の作成や提出代行が主な業務範囲となり、書類面でのサポートが中心です。
一方、税理士は「財務・会計面のアドバイス」が強みです。
収支計画の妥当性チェックや税務面でのアドバイス、創業後の経理サポートまで一貫して対応できます。
特に店舗型ビジネスでは、物件費・内装費・設備費・人件費など複雑な資金計画が必要となるため、財務面での専門知識が重要です。
このような場合、創業融資の申請だけでなく、創業後の経営まで見据えたサポートができる税理士の方が適している場合が多いです。
創業融資はあくまでスタート地点であり、その後の経営が本番です。
長期的な視点で専門家を選ぶことが、創業成功への近道と言えます。
創業融資の申請に必要な書類と準備物
創業融資の申請には複数の書類と準備物が必要となります。
主な必要書類は以下の通りです:
・創業計画書(事業内容、市場分析、収支計画などを記載)
・住民票
・身分証明書のコピー
・確定申告書(過去の収入を証明するもの)
・借入申込書
・創業関係費用の見積書
・店舗の賃貸契約書・見取り図
・開業までのスケジュール表
特に重要なのは創業計画書です。
これは単なる書類ではなく、あなたの事業の将来性を金融機関に伝えるための重要なツールです。
※創業計画書はすべての提出書類の目次の役割も果たしています。
また、面談に備えて以下の準備も必要です:
・自己PRの練習(なぜこの事業か、なぜあなたなのか)
・想定質問への回答準備
・市場調査データの整理
・競合分析の資料
これらの準備を怠ると、書類が通っても面談で断られるリスクがあります。
専門家に依頼する場合は、書類作成だけでなく面談対策までサポートしてくれるかどうかも確認しましょう。
報酬体系の違いとコストパフォーマンス
行政書士と税理士では報酬体系に違いがあり、コストパフォーマンスも異なります。
行政書士の報酬体系は主に以下の2種類です:
・固定報酬型:書類作成や申請代行に対して固定額(10〜30万円程度)
・成功報酬型:融資成功時に融資額の一定割合(3〜5%程度)
一方、税理士の報酬体系はこうなります:
・固定報酬型:書類作成や申請代行に対して固定額(行政書士より若干高め)
・成功報酬型:融資成功時に融資額の一定割合(3〜5%程度)
・顧問契約型:月額固定(1万円〜)で継続的にサポート
コストパフォーマンスを考える上で重要なのは、単に料金の高低ではなく「何が含まれているか」です。
例えば、税理士の場合は融資後の記帳指導や確定申告までサポートしてくれる場合があります。
特に店舗型ビジネスでは、創業後の経営管理も重要となるため、長期的な視点でのサポート体制を重視すべきです。
「通らなければ無料」という成功報酬型は魅力的ですが、それだけでなく「必要な金額を借りられるか」という点も考慮しましょう。
公庫と銀行の併用融資で成功率を高める方法
公庫と銀行の併用融資戦略は、必要な資金を確保するための効果的な方法です。
日本政策金融公庫と銀行では、融資の特徴が異なります:
・公庫:創業者向け融資制度があり、金利が低め。担保や保証人が不要の場合も多い
・銀行:審査はやや厳しいが、条件次第で高額融資も可能。関係構築が重要
これらを併用することで、以下のメリットがあります:
・必要十分な資金を確保できる
・資金使途に応じた最適な融資を受けられる
・複数の金融機関との関係構築ができる
併用融資の成功率を高めるポイントは:
・まず公庫で審査を通し、その承認を銀行融資の材料にする
・公庫と銀行で同じ事業計画書を使うのではなく、それぞれの特性に合わせた資料作成
・銀行との関係構築を早めに始める
ただし、併用融資は戦略的なアプローチが必要であり、専門家のサポートが重要です。
税理士の中でも、元銀行員とチームを組んでいるような専門家なら、審査側の視点を踏まえたアドバイスが期待できます。
面談対策と審査通過のためのアドバイス
創業融資の面談は書類審査と同様に重要で、ここでの対応が融資の成否を左右します。
面談で審査担当者が見ているポイントは主に以下の3点です:
・事業への理解度と熱意
・返済能力と事業の継続性
・人柄と信頼性
面談を成功させるための対策として:
・想定質問への回答を準備する(なぜこの事業か、競合との差別化など)
・数字の根拠を明確に説明できるようにする
・業界知識や専門用語をわかりやすく説明できるようにする
・清潔感のある服装と落ち着いた態度を心がける
また、融資担当者は銀行員や公務員であり、彼らの視点や考え方を理解することも重要です。
例えば、過度に楽観的な計画よりも、リスクも考慮した現実的な計画の方が信頼を得やすいです。
面談対策については、元銀行員などの金融機関経験者からアドバイスを受けることが効果的です。
審査する側の視点を知ることで、より説得力のあるプレゼンテーションができます。
店舗開業なら税理士に依頼するのがおすすめ
店舗型ビジネスの創業融資では、税理士に依頼することをおすすめします。
店舗開業には物件費・内装費・設備費・人件費など、多額の資金が必要となります。
これらの資金計画を精緻に立て、必要十分な融資を受けるためには財務・会計の専門知識が不可欠です。
税理士は財務面のプロとして、以下のようなメリットがあります:
・収支計画の妥当性チェックと改善提案
・税務面を考慮した最適な創業形態のアドバイス
・創業後の記帳指導や確定申告などの継続サポート
・金融機関との交渉力
特に店舗型ビジネスでは「通る」だけでなく「必要な金額を借りる」ことが重要です。
妥協のない開業を実現するためには、物件・設備・人件費などをカバーできる融資計画が必須であり、その点で税理士のサポートは大きな価値があります。
また、創業融資はあくまでスタート地点です。
創業後の経営管理や税務対応も見据えると、最初から税理士と関係を構築しておくことが長期的な成功につながります。
なかでもおすすめは大阪創業融資センター
創業融資のサポートを受けるなら、大阪創業融資センターがおすすめです。
大阪創業融資センターは店舗型ビジネスの創業融資に特化しており、以下の強みがあります:
・日本政策金融公庫と銀行の併用融資支援に実績あり
・元銀行員と税理士がチームで対応
・5億円超の融資支援実績と98.5%の高い成功率
・通らなければ完全無料の成功報酬制
特に店舗開業を考えている方には、物件・内装・設備まで見据えた「リアルな資金計画」の策定から、金融機関との交渉、面談同行まで一貫してサポートしてくれます。
また、融資後も顧問契約で3ヶ月のアフターサポートが付くため、創業初期の不安な時期も安心です。
大阪市・北摂・兵庫南東部なら対面でのサポートも可能ですが、オンラインなら全国対応しています。
多くの起業家が「書類は整ったけど、面談でどう対応すればいいかわからない」という不安を抱えていますが、元銀行員とのチーム対応により、審査側の視点を踏まえたアドバイスが受けられるのも大きな強みです。
「通る」だけでなく「必要な金額を借りる」ことにこだわりたい方には、特におすすめのサービスと言えます。
まとめ
ここまでのポイントをまとめます。
– 創業融資には日本政策金融公庫融資と銀行融資があり、店舗型ビジネスには高額な資金が必要
– 行政書士は主に申請書類作成と提出代行を担当し、戦略的アドバイスや交渉は業務範囲外の場合が多い
– 公庫審査では「返済可能性」と「事業の継続性」を示す具体的な事業計画が重要
– 創業計画書は単なる数字の羅列ではなく、事業の将来性を伝える重要なツール
– 融資の斡旋には「貸金業」または「銀行代理業」の登録が必要で行政書士資格だけでは不可
– 税理士は財務・会計面のアドバイスが強みで、創業後の経営サポートも可能
– 創業融資申請には創業計画書を含む複数の書類と面談対策が必要
– 公庫と銀行の併用融資戦略で必要十分な資金確保が可能
– 店舗型ビジネスの創業では税理士への依頼がおすすめ
– 元銀行員と組んだ専門家なら審査側の視点を踏まえたアドバイスが期待できる
創業融資では行政書士は書類作成のサポートが強みですが、店舗開業には財務面の専門性も重要です。
行政書士と税理士の役割の違いを理解し、あなたのニーズに合った専門家を選ぶことで、必要な金額を確実に調達し、開業の夢を実現できます。
「融資の成功は一時の勝利、その先の経営こそが真の戦場である。」
創業融資は単なるスタートラインに過ぎない。
その先の長い経営の道のりを見据え、書類作成だけでなく経営の伴走者となる専門家を選ぶことが、真の意味での「融資の成功」である。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
近畿税理士会所属 税理士番号:127208
DREAM GATE認定アドバイザー

大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導