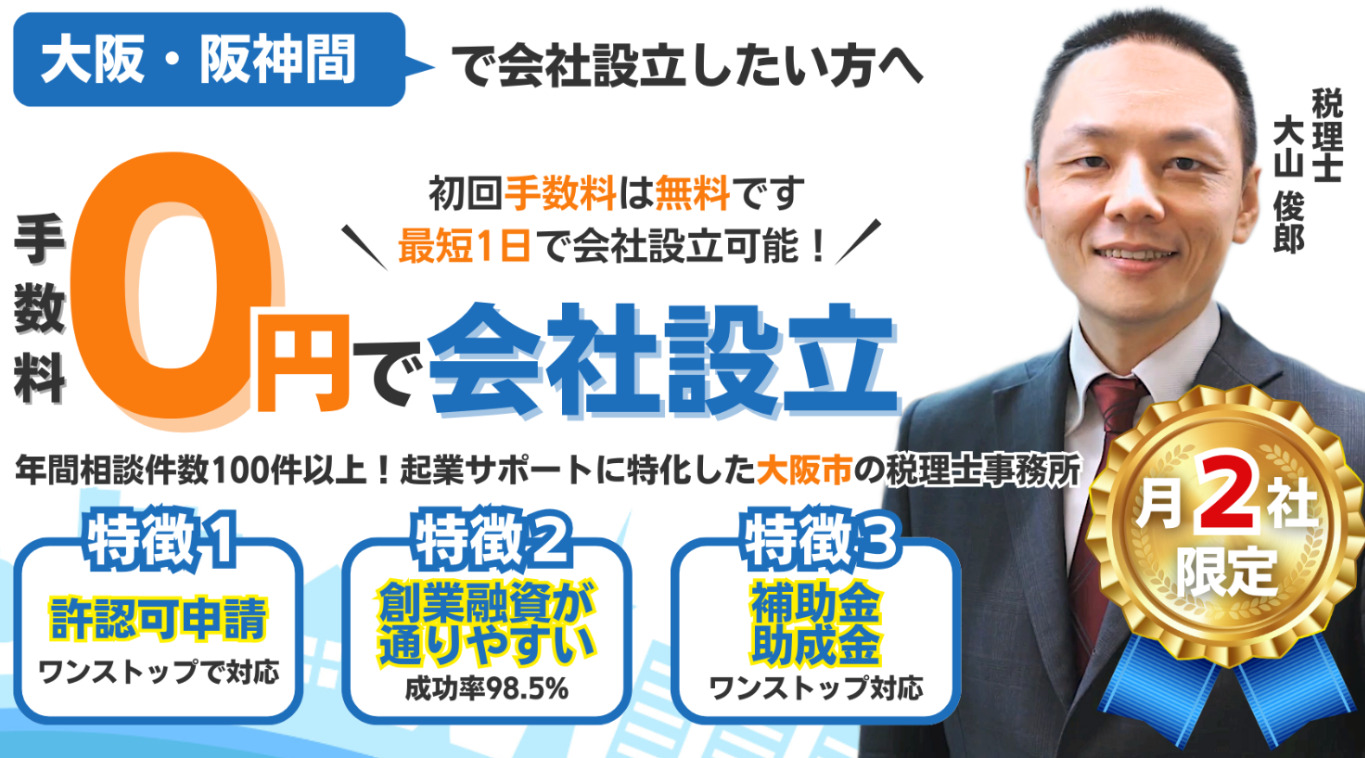【最新版】インボイス登録番号とは?「T」の意味は? | 税理士が取得メリットを解説!
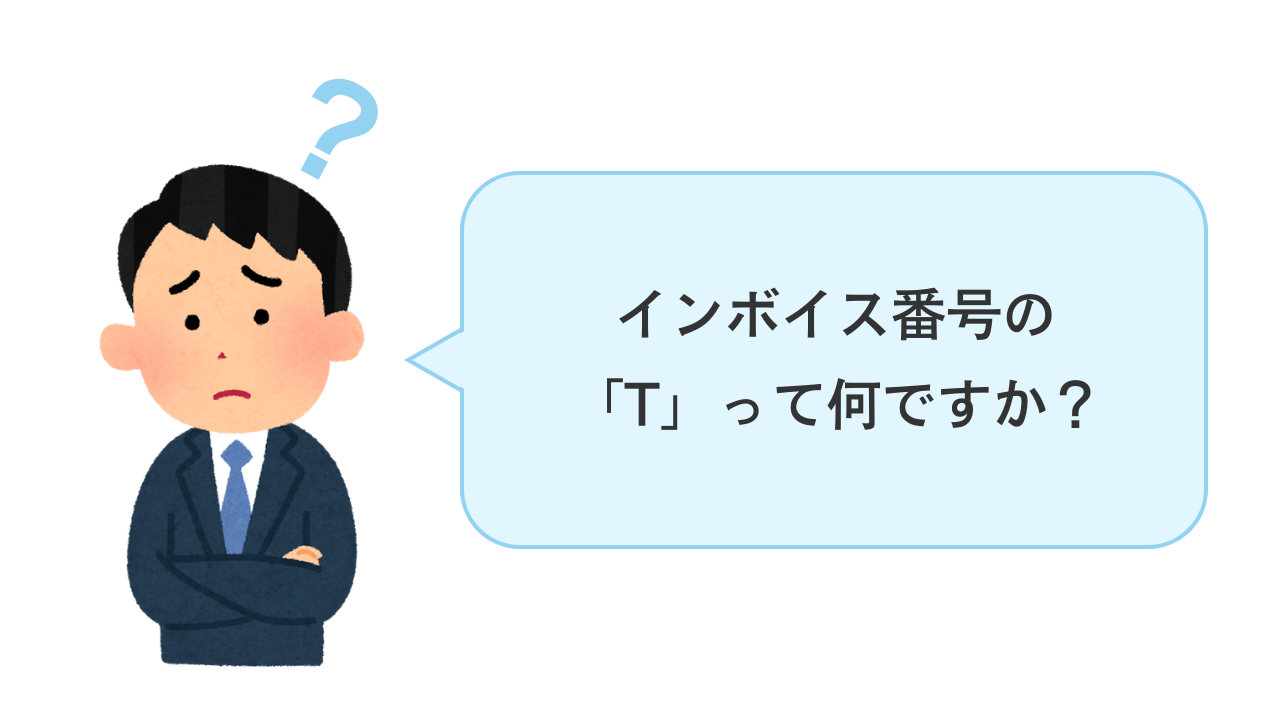
大阪で会社を作るなら、地元大阪の大山俊郎税理士事務所がサポートします!
大山俊郎税理士事務所は、大阪市営地下鉄谷町四丁目駅から徒歩3分。
\年間問い合わせ100件以上/
インボイス制度の登録番号の成り立ちと、意味
登録番号は、「T」+法人番号または「T」+13桁の数字で成り立っています。
「T」は「Tax」(税)の頭文字であり、「T」+法人番号または「T」+13桁の数字は各事業者に割り振られる識別子(しきべつし)です。
インボイス制度登録番号の種類(法人・個人)
インボイス制度登録番号は、事業者が法人であるか個人であるかによって異なります。
法人の場合
法人の場合は、「T」+法人番号となります。
法人番号とは、国税庁が発行する12桁の数字で、各法人ごとに割り振られる識別子です 。
個人の場合
個人の場合は、「T」+13桁の数字となります。
13桁の数字は、国税庁が発行するランダムな数字で、各個人に一意に割り振られる識別子です 。
登録番号が重複しない仕組み
また、登録番号が重複しないようにするために、国税庁では以下のような仕組みを採用しています 。
法人番号は、国税庁が管理する「法人番号管理システム」で一元的に発行されるため、同じ法人番号が二つ以上存在することはありません。
13桁の数字は、国税庁が管理する「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で一元的に発行
されるため、同じ13桁の数字が二つ以上存在することはありません。
「T」+法人番号と「T」+13桁の数字は、それぞれ異なる文字数で構成されているため、混同されることはありません。
インボイス登録番号が必要な理由

2023年10月1日(施行開始日)から始まったインボイス制度とは、消費税の課税方式のことで、仕入税額控除の新しい方式です。
この制度では、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える「インボイス(適格請求書)」を発行する必要があります。
インボイスには、「登録番号」というものが必ず記載されています。
これは、国税庁に登録した「適格請求書発行事業者」であることを証明する番号です。
インボイス制度を理解しないまま事業を経営してしまうと損害を被ることがあります。
まずはこの記事で、インボイス制度について理解してから行動することをおすすめします。
インボイス登録番号の取得方法
【インボイス登録番号を取得する5ステップ】
STEP1 課税事業者かどうかを確認する
インボイス登録の要件は、「課税事業者」であることです。
まずは、自分(自社)が課税事業者かを確認しましょう。
・年間の課税売上高が1,000万円を超える → 課税事業者(登録可能)
・1,000万円以下 → 免税事業者(登録には慎重な判断が必要)
免税事業者のまま番号を取っても、実際にはインボイスは発行できません。登録の前に必ず確認を。
STEP2 必要書類を準備する
登録に必要な書類は以下の通りです。
なお、「人格のない社団」や任意団体も、必要に応じて所轄の税務署へ確認が必要です。登録申請書には法人番号、商号、所在地などの情報が記載されます。
【法人の場合】
・「適格請求書発行事業者の登録申請書」(2枚)
・法人番号
【個人事業主の場合】
・同上の申請書
・マイナンバー(通知カードなど)
書類は国税庁の公式サイトからデータでダウンロードが可能です。
郵送で提出する場合は、押印を忘れないようにしましょう。
国税庁ダウンロードページはこちらです。
STEP3 申請方法を選ぶ
申請には、e-Taxを使った方法のほかに、APIを利用してクラウドサービスなどから直接申し込むこともできます。
A. e-Tax(推奨)
・マイナンバーカードと利用者識別番号を使って、e-Taxから申請
・所要時間はおよそ15〜30分
B. 郵送
・記入した申請書を「インボイス登録センター」宛に簡易書留で郵送
e-Taxは処理が早く、申請履歴の管理もできるため、国税庁も推奨しています。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinsei.htm
STEP4 登録通知を受け取る
申請完了後、以下のいずれかの方法で通知を受け取ります。
・e-Taxの場合:約3〜4週間後に「お知らせ」へ通知
・郵送の場合:約6〜8週間後に通知書が郵送される(時期により前後)
通知書にはインボイス登録番号(例:T+法人番号またはT+13桁の番号)が記載されています。
書面通知を希望した場合、通知書は再発行できないため、大切に保管してください。
※通知書は、事業者が申請後に受領する正式な書類です。
STEP5 登録番号を確認し、業務に反映する
登録に際しては、3つの重要な点を確認する必要があります。以下にその主な活用方法を示します。
取得したインボイス登録番号は、次の用途に活用します。
・請求書や領収書に記載する
・会計ソフトなどに登録する
・取引先に番号を共有する
登録状況の確認や取引先番号の検索は、国税庁公表サイトで可能です。
【補足① 取引先が登録番号を教えてくれない場合の対応】
インボイス登録番号を聞いても返事がない、登録していないと言われる場合は、以下の手順で対応しましょう。
1.まずは丁寧に確認する
登録の有無を聞き、「登録予定があるか」を確認します。
2.制度の必要性と影響を説明する
・登録がないと、こちら側で仕入税額控除ができない
・請求書処理や経理上の影響がある
この点を丁寧に伝えて、協力を依頼します。
3.公表サイトで検索する
相手が教えてくれない場合でも、国税庁のwebサイトで検索して、事業者名・所在地で調べることができます。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
【補足② 取引先の登録番号を管理する方法】
取引先から登録番号を聞いたら、以下の方法で記録・管理しておきましょう。
1.エクセルでの管理(最も簡単)
以下のような項目ごとに区分して、表形式にまとめると便利です。
取引先名(または氏名)|所在地|登録番号|登録日|確認日|備考
2.クラウドや会計ソフトを活用する
freee、マネーフォワード、invoy など、インボイス対応済のクラウドサービスを使えば、検索・確認・更新をデータ上で行うことができるためスムーズです。
履歴保存・連携機能があるため、業務負担も軽減されます。
ポイント
登録番号は将来的に変更や取消の可能性もあるため、定期的な確認も忘れずに。
【補足③ 取引先から登録番号を収集する方法】
登録番号の収集は以下の方法を組み合わせると効率的です。
1.電話で直接確認する
小規模の取引先など、普段からのやり取りがある場合に有効です。
2.メールで一斉送信する
複数の取引先へ依頼する場合はテンプレートを用いて一括送信すると便利です。
件名:インボイス登録番号のご確認のお願い
本文:
平素よりお世話になっております。
インボイス制度対応に伴い、貴社の登録番号(T+番号)をお知らせいただけますと幸いです。
今後の請求書処理等に必要となりますので、〇月〇日まで(必ず年月日を指定する)にご返信をお願い申し上げます。
3.FAXや郵送で案内文を送付する
FAX文化が根強い業界などでは、紙ベースでの案内も検討してください。
4.国税庁の公表サイトで自分で調べる
最終手段として、検索可能な公的サイトから直接確認することもできます。
以上がインボイス登録番号の取得から実務対応までの流れです。
この内容に沿って対応すれば、制度導入後もスムーズに請求書処理・税務管理が可能になります。
必要に応じてこの内容を社内マニュアルや業務手順書として活用してください。
インボイス番号の通知書を紛失したら面倒なことに・・・
国税庁によると、
「書面による通知を希望した方の場合 原則、通知書の再発行はできません。やむを得ない事情で再発行の依頼をする場合、新規申請と同様の処理期間が必要」
また注意すべき点として、原則として再発行はできないようです。
インボイス制度登録番号の確認方法

インボイス制度に対応するためには、まず自分自身や取引先がインボイス制度適格請求書発行事業者として登録されているかどうかを確認する必要があります。
インボイス制度適格請求書発行事業者とは、消費税の税率や税額を記載したインボイスを発行できる事業者のことです。
インボイス制度適格請求書発行事業者の登録状況は、国税庁が公表しているサイトで調べることができます。このサイトでは、以下の方法で検索できます。
自分自身や取引先の登録状況を調べる方法(国税庁公表サイト)
- 法人番号または個人番号(マイナンバー)を入力して検索する
- 事業者名や住所などのキーワードを入力して検索する
- 都道府県や市区町村などの地域別に検索する
検索結果には、以下の情報が表示されます。
- 事業者名
- 法人番号または個人番号(マイナンバー)
- 所在地
- 登録日
- 登録有効期限
登録状況を確認する際に必要な情報
登録状況を確認する際に必要な情報は、以下の通りです。
- 自分自身や取引先の法人番号または個人番号(マイナンバー)
- 自分自身や取引先の事業者名や住所などのキーワード
- 自分自身や取引先の所在地
これらの情報は、事前に準備しておくと便利です。特に法人番号または個人番号(マイナンバー)は、正確に入力しなければなりません。間違えると、登録されているにもかかわらず検索結果に表示されない場合があります。
登録状況が変更された場合の通知方法
インボイス制度適格請求書発行事業者として登録した後も、以下のような場合には登録内容を変更したり取消したりしなければなりません 。
- 住所や名称が変わった場合
- 消費税納税義務が無くなった場合
- インボイス制度適格請求書発行事業者として不適切な行為をした場合
これらの場合には、国税庁へ届出を出す必要があります。届出方法は以下の通りです。
- 電子申告・納税システム(e-Tax)で届出する
- 紙媒体で届出する
※届出後、国税庁から受理通知書が送付されます。
インボイス制度登録番号の確認方法
インボイス制度に対応するためには、まず自分自身や取引先がインボイス制度適格請求書発行事業者として登録されているかどうかを確認する必要があります。インボイス制度適格請求書発行事業者とは、消費税の税率や税額を記載したインボイスを発行できる事業者のことです。 インボイス制度適格請求書発行事業者の登録状況は、国税庁が公表しているサイトで調べることができます。
このサイトでは、以下の方法で検索できます。
自分自身や取引先の登録状況を調べる方法(国税庁公表サイト) – 法人番号または個人番号(マイナンバー)を入力して検索する – 事業者名や住所などのキーワードを入力して検索する – 都道府県や市区町村などの地域別に検索する。
検索結果には、以下の情報が表示されます。
– 事業者名 – 法人番号または個人番号(マイナンバー) – 所在地 – 登録日 – 登録有効期限
登録状況を確認する際に必要な情報 登録状況を確認する際に必要な情報は、以下の通りです。
自分自身や取引先の法人番号または個人番号(マイナンバー)
– 自分自身や取引先の事業者名や住所などのキーワード – 自分自身や取引先の所在地
これらの情報は、事前に準備しておくと便利です。特に法人番号または個人番号(マイナンバー)は、正確に入力しなければなりません。間違えると、登録されているにもかかわらず検索結果に表示されない場合があります。
登録状況が変更された場合の通知方法
インボイス制度適格請求書発行事業者として登録した後も、以下のような場合には登録内容を変更したり取消したりしなければなりません 。
– 住所や名称が変わった場合 – 消費税納税義務が無くなった場合 – インボイス制度適格請求書発行事業者として不適切な行為をした場合
これらの場合には、国税庁へ届出を出す必要があります。
届出方法は以下の通りです。
– 電子申告・納税システム(e-Tax)で届出する – 紙媒体で届出する 届出後、国税庁から受理通知書が送付されます。
請求書や領収書に記載する方法
インボイス制度では、売手側の事業者は取引先から求められた場合に、消費税の税率や税額を記載した請求書(インボイス)を交付しなければなりません。また、買手側の事業者は仕入税額控除をするためには、インボイスを受け取って保存しておく必要があります。
インボイス制度適格請求書発行事業者として登録されている場合には、以下の方法で請求書や領収書に記載することができます。
請求書や領収書に必ず記載しなければならない内容
インボイス制度適格請求書発行事業者として登録されている場合には、以下の内容を必ず記載しなければなりません。
- 発行日
- 発行者の名称
- 発行者の法人番号または個人番号(マイナンバー)
- 受取人の名称
- 受取人の法人番号または個人番号(マイナンバー)
- 売上金額(消費税抜き)
- 消費税率
- 消費税額合計金額(消費税込み)
これらの内容は、明瞭かつ正確に記載する必要があります。
間違えると、仕入税額控除ができなくなる場合があります。
請求書や領収書の作成方法(手書き・パソコン・専用ソフト)
インボイス制度適格請求書発行事業者として登録されている場合には、以下の方法で請求書や領収書を作成することができます。
手書きで作成する
紙媒体で作成し、郵送や直接手渡しで交付する
電子署名を付けたPDFファイル等で作成し、電子メール等で交付する
パソコンで作成する
ワードやエクセル等の一般的なソフトウェアで作成し、郵送や直接手渡しで交付する
電子署名を付けたPDFファイル等で作成し、電子メール等で交付する
e-Tax等の電子申告・納税システムを利用して作成し、電子メール等で交付する
専用ソフトウェアで作成する
インボイス制度対応型会計ソフトウェア等を利用して作成し、郵送や直接手渡しで交付する
インボイス制度対応型会計ソフトウェア等を利用して作成し、電子メール等で交付する
どの方法でも構いませんが、自分自身や取引先と相互に確認したり調整したりしておくことが大切です。
請求書や領収書の保存期間と管理方法
インボイス制度では、請求書や領収書を交換した事業者は、それらを保存しておく必要があります。
しかし、どのくらいの期間保存しなければならないのでしょうか?また、どのように管理すればよいのでしょうか?
ここでは以下の点について解説します。
保存期間
一般的な保存期間
特別な事情がある場合の延長
管理方法
紙媒体で管理する場合
電子媒体で管理する場合
請求書や領収書の保存期間と管理方法 インボイス制度では、請求書や領収書を交換した事業者は、それらを保存しておく必要があります。しかし、どのくらいの期間保存しなければならないのでしょうか?
また、どのように管理すればよいのでしょうか?ここでは、以下の点について解説します。
– 保存期間 – 一般的な保存期間 – 特別な事情がある場合の延長 – 管理方法 – 紙媒体で管理する場合 – 電子媒体で管理する場合
保存期間
インボイス制度では、請求書や領収書を交換した事業者は、それらを保存しておく必要があります。しかし、どのくらいの期間保存しなければならないのでしょうか?
一般的な保存期間
一般的には、請求書や領収書は7年間保存しなければなりません。これは、消費税法に基づく消費税の申告や納付に関する帳簿や書類の保存期間と同じです。つまり、インボイス制度によって新たに設けられた特別な規定はありません。
特別な事情がある場合の延長
ただし、特別な事情がある場合には、7年間よりも長く保存する必要があります。例えば、以下のような場合です。
- 国税庁から調査や検査を受けている場合
- 裁判所や行政機関から証拠提出を求められている場合
- 消費税の還付申告をしている場合
- 消費税の更正処分を受けている場合
これらの場合には、調査や検査等が終了するまで、または更正処分が確定するまで、請求書や領収書を保存しなければなりません。
大阪で会社を作るなら、地元大阪の大山俊郎税理士事務所がサポートします!
大山俊郎税理士事務所は、大阪市営地下鉄谷町四丁目駅から徒歩3分。
\年間問い合わせ100件以上/

大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導