「会社の設立日はこの日にしたい!」「いつできるの?」に税理士の立場からお答えします
「会社を設立するなら設立日はこの日がいい!」
設立日にもこだわりたいというお客様が意外と多いようです。
また年度末になると、3月になると4月から起業したいので年度内に準備して「4月1日を設立日にしたい」なんて声もよく聞きます。
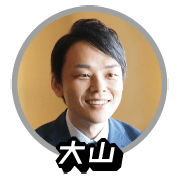
せっかくの起業ですから、設立日を大事にしたい、こだわりたいお気持ち当然です。
ただ知っておいていただきたいのは、会社設立の手続きは時間がかかるケースもある、ということ。
インターネットの情報でたまに「今日言って明日にでも会社設立できる」という記載を見ることがあります。全くの誤情報とは言い切れませんが、いつもその限りであるとは言えないのが正直なところ。
今日はお客様によく聞かれる
- 「会社の設立日この日にしたいねん!いつまでにできるんですか?」
- 「設立日っていつになるのん?」
この疑問にお答えしたいと思います。
そもそも会社設立業務は税理士の領域ではない!だけど…
会社設立について税理士である僕にご相談いただくことが多々あるのですが、実のところ会社設立業務の実務をするのは税理士ではありません。司法書士さんの領域です。
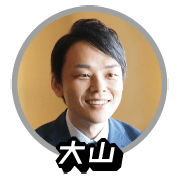
では税理士に会社設立の相談しても意味がないか?と言われたら全くそんなことはありません。むしろ僕たち税理士にまず相談してほしいと思っています。
会社設立業務は税理士がするわけじゃないのに、なぜ税理士に相談した方がいいのか?次にその辺のことについてお話させてください。
税理士に会社設立を相談するとこんな面でいい!
会社設立について税理士に頼むメリットは僕は2つあると思っています。
その1:会社を設立する前に税理士と相談することで節税になることが多々ある
会社設立の流れをこのあとご説明しますが、設立業務を実際行うのは司法書士さんです。彼らは会社設立業務においてはプロです。しかし税金面においてはそうではありません。
会社を設立する際に定款といって会社の決まりを作るのですが、その際役員報酬の設定や、会社設立日について決めないといけません。
役員報酬は多ければ所得税が増え、法人税が減りまるから税理士にご相談いただくことで最適なバランスをご提案できます。また設立日も戦略的に決めることで消費税の納税をなるべく遅くすることも可能です。
そういったご提案ができるのは、会社設立を税理士にご相談いただく最大のメリットだと考えています。
その2:全てのオペレーションを把握してくれるコンシェルジュとしての役割
このあと会社設立の流れを書きますが、正直結構ややこしいです。
- 市役所に行ったり
- 公証役場の予約をしたり
- 法務局に行ったり
- 公証役場に行ったり
いろいろ手続きがあるんですが、ご自分で市役所に行かないといけない場面もあるし、司法書士さんに法務局に行ってもらう場面もあります。
いつ、どこで、だれがの部分がものすごく見えにくいんですよね。
ちなみにこういう記事も書いています。
https://oyama-toshiro.com/wp/establishment-expenses/
それでもわかりにくい会社設立の流れ。
税理士にご相談いただくことで、税金面でのご相談にのりつつ、今どの段階でだれがどこに行かないといけないのか?全てを把握したうえでのお話、つまりコンシェルジュ的な役割ができることもメリットと言えるでしょう。
ややこしい会社設立の流れを書いてみます。これ1日で終わると思いますか?
会社設立の流れを書いてみます。もちろん一人で全てすることも可能ですが、意外とややこしいのです。
見出し部分にやるべき内容と( )の部分にはそのオペレーションをする人を記載しています。
step1:個人の印鑑証明をとる、社名を決める(お客様が)
まずはあなた個人の印鑑証明が必要なので、市役所等で取り寄せてください。
また社名もこのタイミングで決めておいてくださいね。
↓
step2:会社の印鑑を発注する(お客様が)
社名を決めたら会社の印鑑を注文できます。
印鑑が届いたら下準備完了です。
- 印鑑証明
- 社印
この2点を税理士にお渡しください。
実務レベルのお話をするとここから先は司法書士さんの領域なので、弊所にご依頼いただいた場合は、いつもお世話になっている信頼のある司法書士さんに手続きを依頼しています。
ただその前に僕とお客様で先に打ち合わせておくことで、税金面で後々有利になるようなアドバイスをさせていただくことができます。
↓
step3:税理士と打ち合わせ(お客様と税理士で)
税理士と打ち合わせしながら中で定款を作っていきます。
- 何のビジネスを行うのか?
- 決算日はいつか?
- 役員は?
- 資本金は?(1000万円未満推奨)
などを決めていきます。
決算日、役員、資本金はどう設定するかで税金が大きく変わってきます。
ですからこの段階で税理士にご相談いただくと節税効果が高いので、ぜひ覚えておいてくださいね。
↓
step4:資本金の振込証明を確認してもらう(お客様が司法書士に)
この先の手続きとして司法書士さんに法務局へ行って手続きしてもらいます。その際資本金の証明書を渡すのですが、まれにこの証明書の不備で差し戻しになる場合があります。
基本的には設定した資本金がきちんと口座にあることを証明できればよいのですが、その証明を司法書士さんに先に見てもらっておいた方がスムーズです。
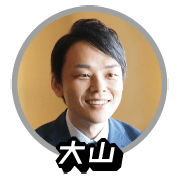
どういう場合に差し戻しになるかというと、例えばインターネットバンキングの場合画面のコピーの場合全画面を印刷できていないのでだめだと言われたケースが過去ありました。
↓
step5:希望の会社名が使用できるかどうか法務局で確認(司法書士)
希望の会社名が使用できるかどうか事前に司法書士さんに法務局で確認をとってもらいます。
同一住所に、同名の会社がすでにある場合には、希望する会社名で登記をすることができないからです。
↓
step6:公証役場に予約(司法書士)
公証役場に行く場合、事前に「公証人」に予約を取らないといけません。
(この予約は司法書士さんが行ってくれます。)
この予約が取れなければ、定款の認証を受けることができず、会社の設立日が遅れることになります。
つまり、「明日、会社を設立したい!」と思っても公証役場の公証人の日程が空いていなければその分、会社の設立が遅れるのは仕方のない事なのです。
↓
step7:公証役場で定款の認証をもらう(司法書士)
定款とは「どういうルールに基づいてビジネスします」という憲法のようなものです。
内容に不備があれば修正しないといけない場合もあります。
特に、定款の中にある「会社の目的」は、法務局の管轄なので法的に通る表現にしないといけません。
公証人は、書類の過不足などの形式チェックをしてくれます。
↓
step8:法務局に登記申請する(司法書士)
登記申請書と7で認証された定款を法務局へ提出しに行きます。これが登記です。
登記した日=会社の設立日なので、会社の設立日にこだわりたい!という方はこのタイミングが希望日になるよう段取りが必要です。
登記した日のおおよそ1週間後に登記簿謄本と印鑑証明書を取得しに行きます。
ちなみに登記、つまり会社を設立したあとも手続きがたくさんあります。
詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
https://oyama-toshiro.com/wp/create-a-company-establish/
【会社設立いつできる?設立日は?の回答】1週間はゆとりをもっておいてください
- 法務局や公証役場などいろんな場所へいかないといけないこと
- 手続きで不備があるとその練り直しで遅延する可能性があること
- さらに役所は土日休みなのでもともと稼働できる日が少ないこと
- 司法書士に依頼する場合は司法書士の忙しさに依存すること
- 退職時期はお客様ご自身も忙しいことが多く連絡がつきづらいこと
先ほど工程をみていただければこういうことはしょっちゅうあります。
つまり、全てが順序良くいけば会社設立は1日でできる場合もある。
だけどそうでない場合も多々あると思っておいてください。
というわけで、会社設立日にこだわりたい方は、1週間はゆとりを持って税理士に依頼してください。
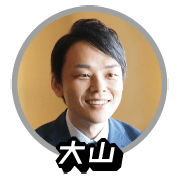
会社員の人はまだ勤めてる状態の人は特に忙しいので、なので早めに動いた方がいいですよ。
まとめ
「会社設立日いつになる?」
というお客様様からよく聞かれることを記事にしてみました。
ちなみにこの一連の会社設立の手続きは、税理士や司法書士に頼まずとももちろん自分でもできるので、ご自分で挑戦されるのも方法の一つです。
ただ独立して早速仕事で忙しい方にとっては少々大変な作業かもしれません。時間の節約になって効率がいいというのはもちろんですが、税理士にご相談いただくことで大幅な節税になります。僕の事務所でももちろんご相談承っておりますのでお気軽にお問い合わせくださいね。
電話でもお申し込みOK
06-6940-0807
【受付時間】10:00〜18:00(土日祝除く)

大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導




